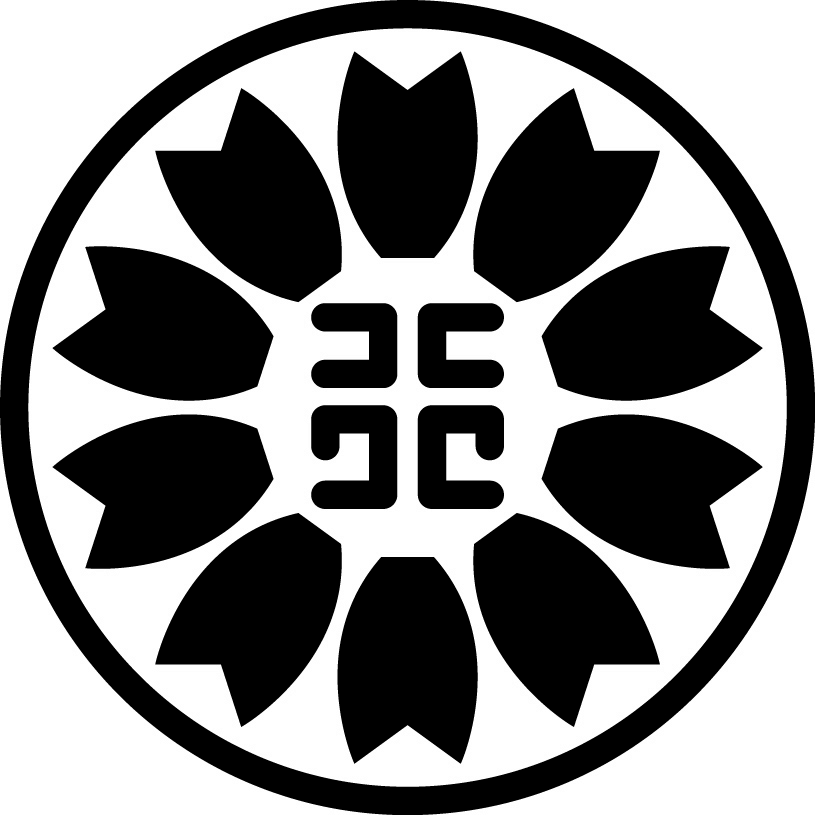フリーランス・個人事業主のための契約書サポート業務委託契約書の読み方

業務委託契約書で読むところは「取り決めた内容が正しく書かれているかどうか」です。具体的には、何の作業をいつまでに完了して、いくらの報酬をいつまでに支払ってくれるのかということです。契約書には決められたフォームや決まった内容はありませんが、「どんな業務を委託するのか」,「その対価として報酬の支払いはどうするのか」といったことが業務委託契約の本質であり基本です。
契約書面の役割
契約は口約束だけでも成立します。口頭で業務の依頼を受け、期日までに作業を終え、相手側から期日通りに報酬も支払ってもらい、依頼業務が完了した。といったときは、契約書を作成していたとしても契約書の出番はありません。何が書いてあったかなど気にしないと思います。ですが、「報酬が減額された」、「期日までに支払ってくれない」、「完了したのに追加で作業を依頼された」など約束と違うとなったとき、どういった約束だったかが問題となり、契約書面の出番です。口頭だけだと、よくある「言った、言わない」の争いになりかねません。あるいは、「そのような意味ではない」、「その内容は含まれていません」といったような、お互い都合の良い解釈のまま作業に着手するといった問題が起こりえます。
フリーランス・個人事業主としてビジネスをスタートしたら直面するのが契約であり、契約書です。依頼者(委託者)から何らかの作業の依頼を受け、それに対して報酬を支払ってもらうというビジネス形態がほとんどだと思います。その「何をして」「いくらもらう」という約束が契約であり、その約束の内容を書面に書き記したものが契約書になります。
フリーランス・個人事業主として
契約書が読めると、仕事がもっと自由になります。
自ら契約書を提示できるフリーランス・個人事業主は
依頼者から信頼を得ることができます。
提示された契約書に署名するだけではなく、自ら契約書を提示できるフリーランス・個人事業主は依頼者から信頼を得ることができます。自ら提示する契約書は、あなたの仕事やサービスの価値を言語化し、誠実さを伝える信頼の設計図となります。行政書士があなたの仕事やサービスに合わせて、わかりやすく、安心できる契約書を設計します。
業務委託契約書にはどのようなことが書いてあって、どこを確認するか?
業務委託契約書とは
そもそも業務委託契約とは、「委託」という言葉から推測できるように、一定の業務を他の者に任せる(依頼する)契約です。法律上の明確な定義はなく、分類するとすれば、民法上の委任契約,準委任契約あるいは請負契約が考えられますが、実態は契約ごとに異なる可能性があります。本質は「委託者が一定の業務を他の者に委託する」,「委託者が委託した業務の対価として受託者に報酬を支払う」、この2点を内容とする契約です。ただ、「委任」と解された場合、報酬に関する取り決めがなければ、無報酬が原則ですが、実社会で無報酬は現実的ではありません。業務委託契約書とは業務委託契約で取り決めた内容を書面に書き記したものが、業務委託契約書です。
確認するポイントは?
委託者から業務の依頼があり、それを引き受けることで契約が成立するわけですから、納期や報酬など、そこには何らかの取り決めがあるはずです。契約書には決められたフォームや決まった内容はありませんが、まずは、その「取り決めた内容が正しく書いてあるかどうか」が基本です。具体的には、「いつまでに」、「何をすればよいか」。依頼者は「いつまでに」、「いくらの報酬を支払ってくれるのか」。「支払の条件は何か」といったことが基本になります。その他には、業務の遂行方法や支払方法,期日,途中解除などを確認します。
あまり気にしなくてよい『契約書のタイトル』と気にすべき『契約の当事者』
契約書のタイトル
一般的に契約書の最初にタイトルがあり、次に契約目的や権利・義務などの個別具体的な内容が置かれています。契約書のタイトルは単に「業務委託契約書」とある場合や、「○○○○業務に関する委託契約書」と具体的な業務名が書いてある場合など色々です。法律的には契約書のタイトルにはあまり意味はなく、本文の内容が契約内容を決めます。極端な話、契約書のタイトルが「売買契約書」となっていても本文の内容が業務を委託する内容であれば、業務委託契約書と解釈されます。とはいえ、タイトルを読めば、書いてある内容がイメージできるような実態を反映した具体的なものを付けるべきです。
契約の当事者
フリーランス・個人事業主が依頼者から業務の依頼を受けることを前提としているので、「受託者」はフリーランス・個人事業主の個人名が記載されているはずです。あるいは屋号があれば、屋号を含めて「○○○○(屋号)こと□□□□(個人名)」と記載されていることもあります。いずれの場合でも、契約の当事者の確定は重要な内容です。契約は原則として、申し込みの意思表示と承諾の意思表示の合致により成立することになっているので、当たり前ですが、当事者間の合意が必要となります。つまり、当事者が特定されていなければ合意そのものが成り立たないことになります。また、契約の当事者は、契約上の地位(権利や義務)が帰属する主体となります。特に、委託者(依頼者)が企業の場合、通常、部署や社員ではなく、企業自体が契約の当事者となるため、部署名や社員名だけの場合は確認する必要があります。
契約書に書いていないことや決めていなかったことはどうなるのか?
「契約書に書いていない内容」や「決めていなかったことはどうなるのか」といったことがよくわからないため、フリーランス・個人事業主の方が契約のことは難しい感じるかと思います。業務委託契約書に書かれていない内容については、2つのことが考えられます。当事者間で取り決めはあるが、書面に書いていない場合と取り決め自体が無い場合です。取り決めはあるが書面に書いていない場合、原則、契約は口頭のみでも成立するので、書面になくても取り決めた内容に従います。ただ、当事者間で相違があったときには、書面に書かれていない取り決め内容を証明することが難しくなります。
決めていなかったことについては、法律に従います。業務委託契約の内容が「請負契約」あるいは「(準)委任契約」のそれぞれについて、法律の規定に従います。いずれにしても、取り決めた内容は書面に記載するようにし、相手側から提示された契約書はきちんと読んで漏れなどないか確認するようにしましょう。ただ、2024年から施行された『特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律』(いわゆる「フリーランス保護新法」)により、書面による取引条件の明示や報酬支払期日の設定などが義務付けられるようになっています。
ご相談,お問い合わせ
業務委託契約について、疑問点,不明点等あればお気軽にご相談、お問い合わせください。
お役立ち記事

利用規約や同意書の書き方と作成するときのポイント 業務委託契約書を作成する時の基本となる条項例 業務委託契約書を作成する時に検討する法的性質 秘密保持契約書に署名を求められたときに確認する条項のポイント 行政書士 辻下仁雄
利用規約や同意書を作る時に検討する内容や書き方の手順について。WebサービスやWebアプリに限らず、自宅サロンや自宅教室など、ご自身が提供するサービスの利用規約や同意書といった書面を準備・・・

業務委託契約書の作成時、検討しなければならない基本となる条項は、契約目的,委託業務内容,報酬,再委託,損害賠償,解除の6項目が挙げられます。委託する業務内容によって色々考えられますが、本質的・・・

業務委託契約という契約は民法の契約には存在しません。「一定の仕事を他の者に任せ、その対価として報酬を支払う」という契約内容を、法的性質という観点から見た場合、大きく分けて受託者に仕事の完成を・・・

秘密保持契約書のレビューや作成時のチェックポイントについて。フリーランスや個人事業主が秘密保持契約書への署名を求められた。業務を委託する、あるいは業務提携を検討しているなど秘密保持契約書を・・・
About Us
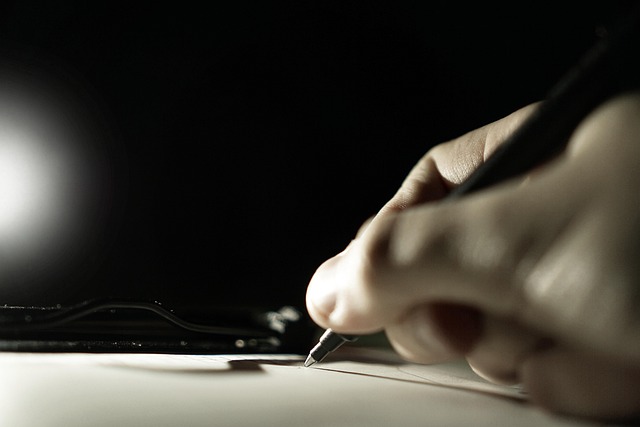
大学で応用数学を学びSEとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業、現在に至る。
神戸市で行政書士事務所を開設している行政書士オフィス辻下の辻下仁雄です。論理的な構成と実務的で説得力ある書類作成を心がけております。ご依頼者一人ひとりに合わせたオーダーメイド対応で画一的なテンプレートではなく個別最適化された書類をご提案致します。細やかな条件がからむ案件でもご相談ください。
権利義務書類,ビザ申請在留手続き書類,許認可申請書類などの書類作成

神戸 行政書士オフィス辻下
〒651-1145 兵庫県神戸市北区惣山町4丁目18ー7
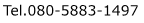 営業時間 10:00〜18:00(土・日・祝祭日 休)
営業時間 10:00〜18:00(土・日・祝祭日 休)
代表 行政書士 辻下仁雄
Profile
大学で応用数学を学び、システムエンジニアとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業し在に至る。
申請取次行政書士 2級ファイナンシャルプランニング技能士