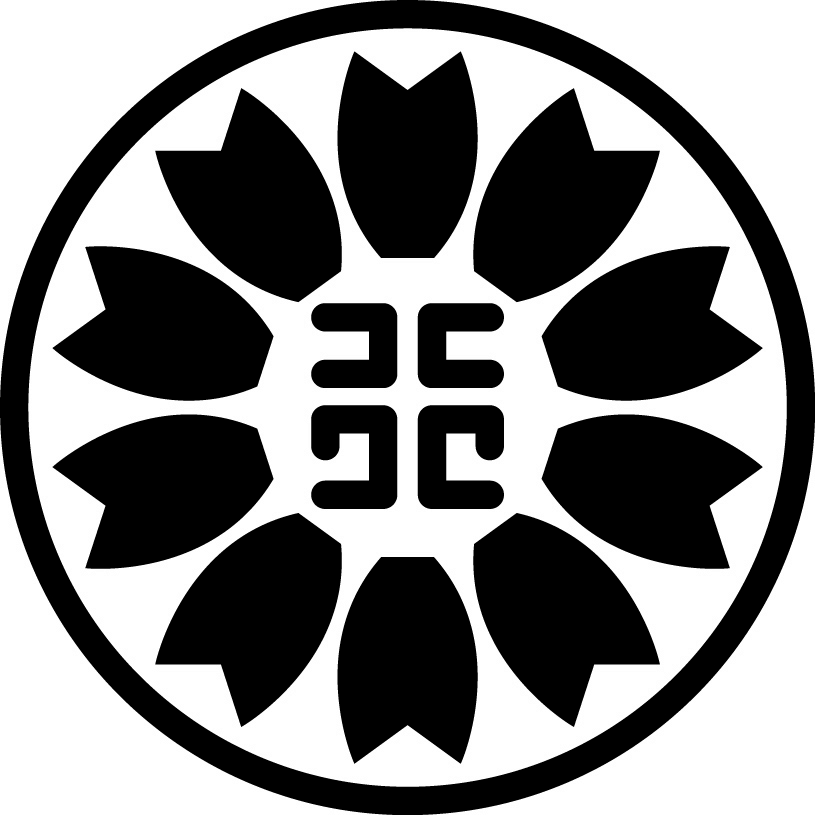フリーランス・個人事業主のための契約書サポート業務委託契約書を作成する時の基本的な条項例
ビジネス契約書などの法律文書

業務委託契約書条項
業務委託契約書を作成するときに検討する基本となる条項は「契約の目的」,「委託する業務内容」,「報酬」,「再委託」,「損害賠償」,「解除」が挙げられます。この契約は委託する業務内容によって「請負」か「(準)委任」が考えられますが、本質的には「委託者が一定の業務を他の者に委託する」,「委託者が委託した業務の対価として受託者に報酬を支払う」、この2点を内容とする契約です。
契約書や念書,合意書,借用書などの権利義務書類について、疑問点・不明点等あれば、お問い合わせください。
「委任」と解された場合、報酬に関する取り決めがなければ、無報酬が原則ですが、実社会では無報酬は現実的ではありません。委託する業務の内容によって、「保守業務委託契約」,「コンサルティング業務委託契約」,「市場調査業務委託契約」,「製造業務委託契約」,「システム開発委託契約」等、色々な名前で呼ばれています。委託する業務の内容や目的によって色々ですが、おおよそ共通して必要となる基本的な条項は以下のようなものが挙げられます。
特に2.〜6.の5項目はトラブルの原因となりやすい条項です。
その他参考
1.契約の目的
目的条項を設けずに、契約書の前文として規定する場合もあります。目的条項自体が具体的な契約条件について法的な拘束力を有することは少なく、必ず必要な条項ではないですが、目的を明記することにより取引の内容を特定し、当該委託業務によって委託者,受託者が求めている内容を共通して認識するために明示します。また、契約の各条項の解釈をめぐって紛争が生じた場合には、当該条項を解釈するための指針として、参酌される場合があります。
システム開発委託契約の場合の条項例
第〇〇条(目的)
本契約は、委託者が社内情報システムの設計,開発業務(以下、「本業務」という。)を受託者に対して委託するにあたり、委託者,受託者間にて合意した事項を明確にすることをその目的とする
製造業務委託契約の場合の条項例
第〇〇条(目的)
本契約は、委託者が別紙記載の製品(以下、「本製品」という。)の製造業務(以下、「本業務」という。)を受託者に対して委託するにあたり、その基本的な条件を定めることを目的とする。
2.委託する業務内容
委託する業務の内容が「仕事の完成を目的とする」場合は、請負契約と考えられますが、「仕事の完成を目的とするものではなく、単なる事務処理のようなものを対象とする」場合は委任(準委任)契約と考えられます。例えば、業務委託契約でよく例えられる「市場調査業務」を委託する場合、「市場調査業務の実施のみ」を目的とする場合は準委任契約と考えられます。しかし、「単なる市場調査の実施のみだけでなく、調査結果の分析,販売戦略企画書の作成を行うこと」のように一定の仕事の完成を目的とした場合は、請負契約と考えられます。
請負型契約でも委任型契約でも業務委託契約では最も重要な条項となります。基本的な構成要素の1つでもあり、いかなる業務を委託するのかを具体的に明記します。何を委託したのかが具体的でないと、委任者と受任者の間で、認識のズレが起こる恐れがあります。
市場調査業務の場合の条項例
第〇〇条(実施する業務内容)
受託者は○○年○○月○○日付け「○○企画書」に基づき、以下の業務を実施し提供する。
1.○○の市場調査
2.調査結果の分析と報告書作成
なお、受託者は、調査結果を○○年○○月○○日までに委託者に最終報告するものとする。
市場調査業務の場合の条項例(請負型)
第〇〇条(実施する業務内容)
受託者は○○年○○月○○日付け「○○企画書」に基づき、以下の業務を実施し提供する。
1.○○の市場調査
2.調査結果の分析と報告書作成
3.調査結果に基づき、販売戦略企画書の作成及び、企業の販売コンセプト構築
なお、受託者は、調査結果及び、コンセプトを○○年○○月○○日までに委託者に最終報告するものとする。
コンサルティングの業務委託契約の条項例
第〇〇条(業務内容)
1.受託者は、本件業務を委託者の指示に従い善良な管理者の注意をもって行うものとする。
2.受託者は本業務を次のとおり遂行する。
(1)受託者による○○調査の着手 本契約締結日から〇〇日以内
(2)受託者による○○調査の報告書提出 ○○年○○月○○日限り
(3)委託者による(2)のついての検収 (2)から○○日以内
その他に、調査途中での報告会の回数や、調査方法や手順、報告書に記載する項目等、決めておくことが可能であれば、具体的に記載しておくべきです。
システム開発業務委託契約の条項例
第〇〇条(業務内容)
委託者が受託者に委託する業務(以下、「本業務」という。)は、以下の各業務から構成される。
1.要件定義
委託者の情報システム構想およびシステム化計画等の立案に関し、要件定義を行う。 (成果物) 要件定義書
2.基本設計作業
システム要件の分析とシステム方式設計作業を行う。 (成果物) 基本設計書
3.システム構築作業
上記基本設計に基づきシステム開発を行う。 (成果物) ソースコード一式
おおまかな例ですが、システム開発業務の場合、契約書において仕様書等があれば、それを引用してさらに細かく取り決めておく方が良いです。
3.報酬
2.の委託する業務内容と密接に関係しますが、報酬についても業務委託契約では最も重要な項目の1つです。こちらも基本的な構成要素の1つであり、当たり前ですが「何をすれば」、あるいは「何を完了して、どんな条件をクリアすれば」、「いつ」、「どんな方法で」、報酬が支払われるかを明確にしておきます。
コンサルティングの業務委託契約の条項例
第〇〇条(報酬)
1.委託者は受託者に対して、本業務に対して以下のとおり報酬を支払う。
(1)○○調査の着手
調査に着手後○○営業日以内に金○○円
(2)○○調査の報告書提出
調査報告書について委託者による検収終了後○○営業日以内に金○○円
2.前項に定める報酬については、委託者は受託者が指定する金融機関口座に振り込む方法により支払う。ただし、振り込みにかかる費用は委託者の負担とする。
システム開発業務委託契約の条項例
第〇〇条(報酬)
委託者は受託者に対して、本業務に対してそれぞれの成果物の検収合格後○○営業日以内に受託者の指定する金機関口座に振り込む方法で以下のとおり報酬を支払う。ただし、振り込みにかかる費用は委託者の負担とする。
(1)要件定義 (成果物) 要件定義書 金○○円
(2)基本設計 (成果物) 基本設計書 金○○円
(3)システム構築 (成果物) ソースコード一式 金○○円
第〇〇条(検収)
1.委託者は受託者から成果物が納入された場合は、あらかじめ委託者受託者協議の上決定した検収基準に従って、納入から○○営業日以内に検収を行う。成果物の納入から〇〇営業日以内に委託者から受託者に対して検収不合格の通知がなされなかった場合は、検収に合格したものとみなす。
2.前項にかかわらず、委託者から受託者に対して不合格通知が送付された場合は、受託者は検収基準に合致するよう成果物を修正し、再度委託者の検収を受けるものとし、以下、同様とする。
その他、タイムチャージ(時間制単価)が規定される方法や、毎月末限り金○○円等と記載される場合があります。
4.再委託
通常、委託者は受託者を信頼して業務を任せます。一般的には受託者が業務の全部又は一部を第三者に再委託することは想定されていない場合が多いと思います。ですが、法的に見ると請負型と考えられる場合、請負契約は仕事の完成が目的であるので、その過程で受託者が第三者に再委託することは禁止されていないと考えられます。対して、委任契約の場合は再委託が原則禁止されます。業務委託契約は、上述の委託者の信頼に加えて、請負か委任かの区別が容易でない面もあり、再委託の条項は定義しておくべきです。
原則として再委託を禁止
第〇〇条(再委託)
1.受託者は、委託者の事前の書面による承諾を得た場合に限り、第三者(以下、「再委託先」という。)に対し、本業務の全部又は、一部を再委託することができる。
2.受託者は、前項に基づき再委託を行った場合は、当該再委託先に対し、本契約における受託者の義務と同等の義務を尊守させ、当該再委託先の行為に関して、受託者がしたのもと同じく、一切の責任を負う。
再委託した場合、委託者に通知する義務を定める場合
第〇〇条(再委託)
3.受託者は第1項に基づき再委託を行った場合は、直ちに再委託先の名称及び、再委託した本業務の内容を委託者に書面により通知するものとする。
5.損害賠償
損害賠償の条項を契約書に定めなくても、民法の規定に基づいて、故意又は、過失により契約上の義務に違反して相手方に損害を与えた場合は、相手方に対して損害賠償する義務があります。契約書には注意的にこの条項を定めます。
第〇〇条(損害賠償)
委託者及び受託者は、本契約に違反し相手方に損害を与えた場合は、相手方に対してその損害を賠償しなければならない。
賠償する損害額が莫大になる可能性やあるいは、損害賠償の範囲の予測が難しい場合には、損害賠償額の上限を定める条項を定めます。
第〇〇条(損害賠償)
委託者及び受託者は、本契約に違反し相手方に損害を与えた場合は、相手方に対してその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害賠償額は本契約に基づく報酬額を上限とする。
損害賠償額の上限を故意又は重大な過失を除く場合に限定する場合
第〇〇条(損害賠償)
委託者及び受託者は、本契約に違反し相手方に損害を与えた場合は、相手方に対してその損害を賠償しなければならない。ただし、本契約の違反が故意又は重大な過失による場合を除き、その損害賠償額は本契約に基づく報酬額を上限とする。
6.中途解約
有効期間のある業務委託契約の場合、原則として有効期間内は契約を終了させることはできません。しかし、どうしても契約を途中で終了したい場合に備えて、中途解約の条項を定めます。
事前の通知で無条件で解約する場合
第〇〇条(解約)
委託者又は受託者は、業務の都合等により本契約を継続し難い事情が発生した場合、相手方に対し、書面でその旨を相当な期間を定めて通知することにより、本契約を無条件で解約することができる。
上記の例では、「相当な期間を定めて」とありますが、「〇〇カ月前までに」あるいは「○○カ月以上の予告期間をもって」など、特定の期間を明示的に定める場合もあります。
業務委託契約の法的性質
業務委託契約は業界を問わず企業取引の中でよく使われる契約形態の1つです。よく使われる割には、当事者間の合意内容について法的性質という観点から見たとき、請負か委任かがはっきりしないことがあります。また、委託業務の範囲や対価の支払いの合意が不明確であったりなど、曖昧な理解のまま締結してしまうことも少なくありません。業務委託契約の法的性質についての詳細はこちらの『業務委託契約書を作成するときに検討する法的性質』ページを参照ください。
契約書や合意書,念書などの書類について専門家に聞いてみたいとお考えの方は、お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。
ご相談,お問い合わせ
フリーランスや個人事業主様、書類作成で困り事はありませんか?
契約書,合意書,覚書,念書,和解書,借用書など、個人間でも法的書面化が必要とされる場面があります。
行政書士として、客観的視点と法的観点から、冷静に整理・文書化いたします。
ビジネス契約書などの法律文書関連記事

前の記事
業務委託契約書を作成する時に検討する法的性質
業務委託契約という契約は民法の契約には存在しません。「一定の仕事を他の者に任せ、その対価として報酬を支払う」という契約内容を、法的性質という観点から見た場合、大きく分けて受託者に仕事の完成を約束させる請負と、受託者に事務処理を約束させる委任に分けられます。

次の記事
業務委託契約の解除合意書の条項例
業務委託契約の解除合意書はお互いが契約解除に合意したことを証明する書面です。法律上必ず作らなければならないというものではありません。また、作らなければ契約を解除できなというものでもありません。後のトラブル防止のため、話し合って合意した内容、特に清算条項を書面にします。
その他、よく読まれている記事

借用書は通常、借主側のみが署名,押印するのに対して、金銭消費貸借契約書は借主側,貸主側双方が署名,押印します。借用書や金銭消費貸借契約書を作成する場合、ポイントは、返す約束をしたこと、借主が金銭を受領済であることの明記です。

お金を貸した後から作成するのが債務承認弁済契約書と呼ばれる書類です。お金を貸すときに書類など作成せずに貸したけど、約束の時期になってもなかなか返してくれないなど、不安があるのであらためて書類を作成したいときに作成します。後から作成しても法的問題はありません。

業務委託契約の解除合意書はお互いが契約解除に合意したことを証明する書面です。法律上必ず作らなければならないというものではありません。また、作らなければ契約を解除できなというものでもありません。後のトラブル防止のため、話し合って合意した内容、特に清算条項を書面にします。

個人的なやり取りにおいて、約束した証拠として又は、事実を確認した証拠として交わされることが多い念書。念書に関して、作成する場面、契約書、合意書、覚書等の書類との違いや法的効力、書き方について。

和解契約書とは和解契約で合意した内容を書面にしたものです。書き方の基本は、「当事者」(誰と誰が),「日付」(いつ),「事実関係」(どんな争いがあって),「和解内容」(話し合いでどのように解決するか)です。和解契約とは、当事者双方が話し合いで互いに譲歩して、その間にある争いを止めることを約束する契約のことをいいます。

仮契約という言葉は広く一般的に使われています。ですが、何故「仮」であるのかを考えて、その効力をはっきりさせる必要があります。たとえタイトルに「仮」と記載されていても、その内容がお互いに何らかの義務を負う内容になっていれば、法的な効力を持つ契約書になります。

利用規約や同意書を作る時に検討する内容や書き方の手順について。WebサービスやWebアプリに限らず、自宅サロンや自宅教室など、ご自身が提供するサービスの利用規約や同意書といった書面を準備していますか?
権利義務書類,ビザ申請在留手続き書類,許認可申請書類などの書類作成

神戸 行政書士オフィス辻下
〒651-1145 兵庫県神戸市北区惣山町4丁目18ー7
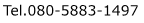 営業時間 10:00〜18:00(土・日・祝祭日 休)
営業時間 10:00〜18:00(土・日・祝祭日 休)
代表 行政書士 辻下仁雄
Profile
大学で応用数学を学び、システムエンジニアとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業し在に至る。
申請取次行政書士 2級ファイナンシャルプランニング技能士