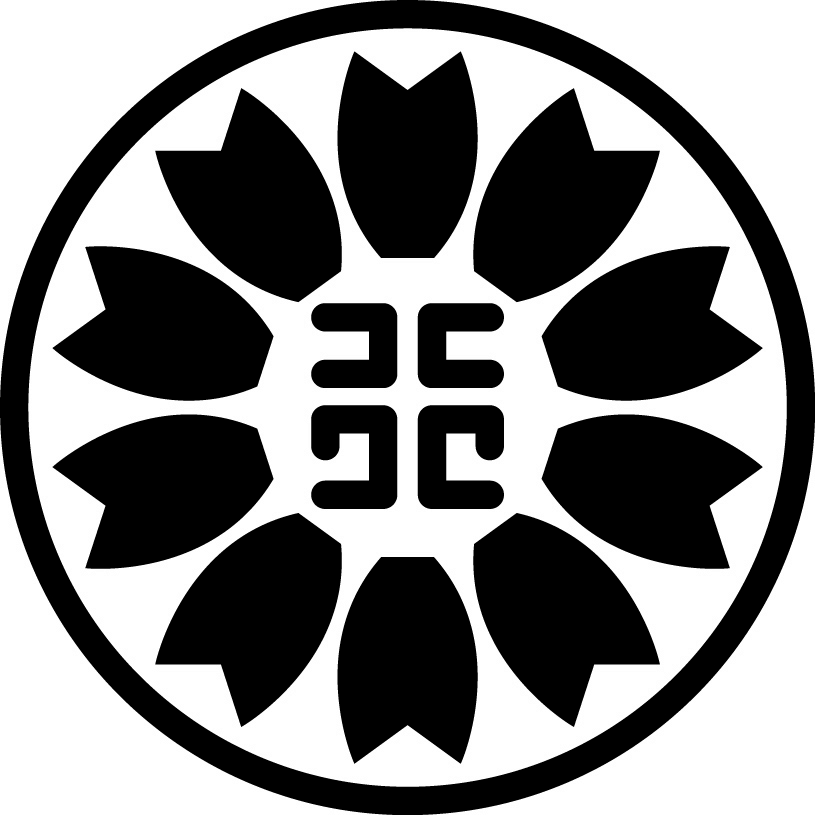日々の暮らしで役立つ法律文書合意書や覚書の具体的な作成例
日々の暮らしで役立つ法律文書
契約書や念書,合意書,借用書などの権利義務書類について、疑問点・不明点等あれば、お問い合わせください。
建物賃貸借に関する作成例
滞納している家賃の返済に関する合意書・覚書例
滞納賃料の支払いに関する合意書・覚書です。記載内容としては、
・賃料を滞納している事実
・滞納賃料の支払い義務があることを認める文言
・滞納賃料(支払義務がある)金額と支払い方法など
<記載例>
覚 書
貸主○○○○(以下「甲」という。)と借主○○○○(以下「乙」という。)は、甲乙間の平成○○年○○月○○日付け建物賃貸借契約(以下「原契約」という。)に関して、次の理由により、以下の通り覚書(以下「本覚書」という。)を締結する。
「理由」
乙が原契約に定める平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日分の賃料合計金○○円の支払いを滞納したこと。
第一条(滞納賃料の支払い)
1 乙は、甲に対し、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日分の賃料合計金○○円の支払い義務があることを認める。
2 乙は、甲に対し、前項の金員○○円を、平成○○年○○月○○日限り、甲の指定する下記銀行口座に振り込む方法で支払う。
ただし、振り込み手数料は乙の負担とする。
「振込口座」
○○銀行 ○○支店 普通預金
口座番号 ○○○○○○ 口座名義 ○○○○
第二条(原契約維持)
甲及び乙は、本覚書に記載なき事項は、原契約に定めるところによることを確認する。
本覚書締結の証として、本覚書二通を作成し、甲乙相互に署名・押印のうえ各一通を保管することとする。
平成 年 月 日
甲 印
乙 印
本例は一括払い,口座振り込みを前提とした記載例です。分割払いにする方法、連帯保証人を別につける方法等があります。また、分割払いにした場合には、分割払いを怠った場合に一括請求できるように期限の利益の喪失条項を規定します。
<分割払いの例>上記例の第一条を以下のように変更します。
第一条(滞納賃料の支払い)
1 乙は、甲に対し、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日分の賃料合計金○○円の支払い義務があることを認める。
2 乙は、甲に対し、前項の金員○○円を、次の通り分割して甲の指定する下記銀行口座に振り込む方法で支払う。
ただし、振り込み手数料は乙の負担とする。
(1)平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日まで、毎月末日限り各金○○円
(2)平成○○年○○月○○日末日限り、金○○円
「振込口座」
○○銀行 ○○支店 普通預金
口座番号 ○○○○○○ 口座名義 ○○○○
<期限の利益の喪失条項例>上記例に以下のような条項を追加します。
第○○条(期限の利益喪失)
乙が第一条第二項の分割金の支払いを怠り、その金額が金○○円に達したとき、または支払いを二回以上怠ったときは、乙は当然に期限の利益を失い、乙は甲に対し、その時点での残金の合計額をただちに支払う。
賃貸人の変更に関する合意書,覚書
所有者が賃貸中の物件を第三者に売却したりして賃貸対象の建物を譲渡した場合、記載する内容としては、
・賃貸人が変更となった事情
・貸主の地位が誰から誰に代わったか
・現状の貸主の地位及び権利義務の承継を明確に
・貸主の地位の変更以外は原契約の維持を明文にする
・当事者は旧貸主、新貸主、借主 などです。
又、貸主が亡くなった場合や、マスターリース契約の終了等で貸主が変更となる場合があります。その他、借主の変更や契約期間の変更等に関する合意書,覚書があります。
金銭消費貸借に関する作成例
以下の金銭消費貸借契約書を原契約として、利息の変更,返済方法の変更,支払期限の変更などに関する合意書・覚書の例
<原契約例>
金銭消費貸借契約書
貸主〇〇〇〇(以下「甲」という。)と借主○○○○(以下「乙」という。)は、以下のとおり金銭消費貸借契約を締結した。
第一条 甲は乙に対し、本日、金○○円を貸付け、乙はこの金額を受領した。
第二条 乙は甲に対し、前条の借入金○○円を平成○○年○○月○○日までに甲に持参または、甲指定の銀行口座に振り込む方法で返済する。
ただし、振込手数料は乙の負担とする。
第三条 乙が前条の返済を怠ったときは、甲より何らの催告なくして、当然に期限の利益を失い、直ちに借入金全額を返済しなければならない。
本契約締結の証として、本契約書二通を作成し、甲乙相互に署名・押印のうえ各一通を保管することとする。
平成 年 月 日
甲 印
乙 印
利息の変更例
原契約締結時は利息を発生しないものとしていたが、これを発生するものとする変更の場合、その旨を明確にすることと、いつから利息を発生させるのかを明確にします。
<記載例>
覚 書
貸主○○○○(以下「甲」という。)と借主○○○○(以下「乙」という。)は、甲乙間の平成○○年○○月○○日付け金銭消費貸借契約(以下「原契約」という。)に関して、次の理由により、以下の通り覚書(以下「本覚書」という。)を締結する。
「理由」
原契約で定めていた利息を変更することとした。
第一条(利息の変更)
甲および、乙は、本覚書締結以降、原契約における利息を以下のとおり変更する。
(変更前) 利息 ゼロ
(変更後) 利息 年○○パーセント
第二条(原契約維持)
甲及び乙は、本覚書に記載なき事項は、原契約に定めるところによることを確認する。
本覚書締結の証として、本覚書二通を作成し、甲乙相互に署名・押印のうえ各一通を保管することとする。
平成 年 月 日
甲 印
乙 印
返済方法の変更例
原契約では持参または、振り込みによる一括返済としていたが、振込による分割払に変更する場合の例。分割払いにする場合は、期限の利益の喪失条項についても見直しが必要となります。
<記載例>
覚 書
貸主○○○○(以下「甲」という。)と借主○○○○(以下「乙」という。)は、甲乙間の平成○○年○○月○○日付け金銭消費貸借契約(以下「原契約」という。)に関して、次の理由により、以下の通り覚書(以下「本覚書」という。)を締結する。
「理由」
甲に対して乙が原契約で定めていた一括払いによる支払い方法を分割払いに変更することとなった。
第一条(利息の変更)
甲および、乙は、原契約における支払方法を以下のとおり変更する。
(変更前) 乙は甲に対し、借入金○○円を平成○○年○○月○○日までに甲に持参または、甲指定の銀行口座に振り込む方法で返済する。ただし、振込手数料は乙の負担とする。
(変更後) 乙は甲に対し、借入金○○円を以下のとおり分割して、甲指定の銀行口座に振り込む方法で支払う。ただし、振込手数料は乙の負担とする。
(1) 平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日まで毎月末日限り、金○○円ずつ
(2) 平成○○年○○月○○日末日限り 金○○円
第二条(期限の利益の喪失)
乙が前条の金員の支払いを一回でも怠ったときは、乙は、当然に期限の利益を失い、甲に対して残金を一括で支払う。
第三条(原契約維持)
甲及び乙は、本覚書に記載なき事項は、原契約に定めるところによることを確認する。
本覚書締結の証として、本覚書二通を作成し、甲乙相互に署名・押印のうえ各一通を保管することとする。
平成 年 月 日
甲 印
乙 印
期限の利益の喪失条項の変更例
期限の利益の喪失事由として、分割金の支払いを怠ったときを記載する場合が多いですが、一回でも支払時期が遅れた場合や、二回以上遅れた場合、あるいは滞納金額が○○円に達した時といった滞納金額の要件をつけたりする場合もあります。
<記載例>
覚 書
貸主○○○○(以下「甲」という。)と借主○○○○(以下「乙」という。)は、甲乙間の平成○○年○○月○○日付け金銭消費貸借契約(以下「原契約」という。)に関して、次の理由により、以下の通り覚書(以下「本覚書」という。)を締結する。
「理由」
原契約で定めていた期限の利益の喪失条項を変更することになった。
第一条(期限の利益の喪失)
甲および乙は、原契約に定める期限の利益の喪失条項を以下のとおり変更する。
(変更前) 乙が第○○条の金員の支払いを一回でも怠ったときは、乙は、当然に期限の利益を失い、甲に対して残金を一括で支払う。
(変更後) 乙が第○○条の金員の支払いを二回以上怠ったときは、乙は、当然に期限の利益を失い、甲に対して残金を一括で支払う。
第二条(原契約維持)
甲及び乙は、本覚書に記載なき事項は、原契約に定めるところによることを確認する。
本覚書締結の証として、本覚書二通を作成し、甲乙相互に署名・押印のうえ各一通を保管することとする。
平成 年 月 日
甲 印
乙 印
債務不存在の確認に関する合意書,覚書
借りた金銭(金銭消費貸借契約)の支払い債務が弁済により消滅した場合、記載する内容としては、
・弁済によって原契約に基づいて発生した全ての債務の履行が完了したことを明確に
・合意書,覚書に定めるほか、何らの債権債務がないことを明確に
・当事者は貸主、借主 などです。
又、第三者の弁済により債務が消滅した場合は、その旨を明確に記載します。その他、相殺により債務が消滅した場合、貸主が放棄した場合等があります。
<記載例>
覚 書
貸主○○○○(以下「甲」という。)と借主○○○○(以下「乙」という。)は、甲乙間の平成○○年○○月○○日付け金銭消費貸借契約(以下「原契約」という。)に関して、次の理由により、以下の通り覚書(以下「本覚書」という。)を締結する。
「理由」
原契約に基づいて発生した乙の甲に対する債務の履行が全てなされたので、債務が存在しないことを確認する。
第一条(弁済による債務消滅)
甲および乙は、原契約に基づいて発生した全ての債務の履行を完了したことを確認する。
第二条(清算条項)
甲および乙は、相手方に対するその余の請求をそれぞれ放棄し、本覚書に定めるほか、何ら債権債務がないことを相互に確認する。
本覚書締結の証として、本覚書二通を作成し、甲乙相互に署名・押印のうえ各一通を保管することとする。
平成 年 月 日
甲 印
乙 印
第二条の清算条項について「本覚書に関して、何ら債権債務がない・・・」と記載すると、本覚書以外の債権債務は残っていると解釈できます。本覚書以外にも借入金の債権債務が存在するのであれば、それでも良いですが、そうでなければ「その余の請求をそれぞれ放棄し、本覚書に定めるほか、何ら債権債務がない・・・」と記載します。「本覚書に関して、何ら債権債務がない・・・」と記載するのは、その他の権利関係が存続している場合、その権利関係に影響を及ぼさないようにするために記載します。
<第三者の弁済により債務の消滅例>
(弁済による債務消滅)
甲および乙は、乙の親である○○○○(以下「丙」という。)の弁済により、原契約に基づいて発生した乙の甲に対する全ての債務の履行を完了したことを確認する。
<相殺による債務の消滅例>
第一条(相殺による債務消滅)
1 甲および乙は、本日現在乙が甲に対して原契約に基づき金○○円の借入金債務を負担していること、甲が乙に対して○○年○○月○○日付け金銭消費貸借契約に基づき金○○円の借入金債務を負担していることをそれぞれ確認し、乙の借入金債務と甲の借入金債務とを対等額で相殺する。
2 甲および乙は、前項の相殺により、原契約に基づいて発生した乙の甲に対する全ての債務の履行を完了したことを確認する。
<貸主の放棄による債務の消滅例>
第一条(放棄による債務消滅)
甲は、原契約に基づいて発生した甲の乙に対する全ての債権を放棄する。
公正証書の作成に関する合意書,覚書
金銭消費貸借契約書を公正証書にし、その契約書に約定どおりに履行されない場合には直ちに強制執行されても異議は唱えないとの文言が記載されていれば、裁判を経ることなく借主の財産に対して強制執行をして貸金の回収を図ることができます。このような執行認諾文言付公正証書を作成することに合意した場合、それを書面として残す場合があります。記載内容としては、
・原契約に基づいて発生する債務の履行について、強制執行されても異議は唱えない旨を記載した公正証書を作成することに合意したことを明確に
・本合意事項以外は原契約に定めるところによることを明記
・当事者は貸主、借主 などです。
又、公正証書を作成する公証役場の場所や作成する日時を明記する場合や、原案の作成者、作成手数料の負担者を明記する場合もあります。
<記載例>
覚 書
貸主○○○○(以下「甲」という。)と借主○○○○(以下「乙」という。)は、甲乙間の平成○○年○○月○○日付け金銭消費貸借契約(以下「原契約」という。)に関して、次の理由により、以下の通り覚書(以下「本覚書」という。)を締結する。
「理由」
原契約について公正証書を作成する旨の取決めをする。
第一条(公正証書の作成)
甲および乙は、原契約について、原契約に基づいて発生する債務の履行につき、直ちに強制執行に服する旨の陳述(強制執行認諾文言)を記載した公正証書を作成することに合意し、そのために必要な手続きを行う。
第三条(原契約維持)
甲及び乙は、本覚書に記載なき事項は、原契約に定めるところによることを確認する。
本覚書締結の証として、本覚書二通を作成し、甲乙相互に署名・押印のうえ各一通を保管することとする。
平成 年 月 日
甲 印
乙 印
<公正証書作成費用の負担者を定める例>
以下のような条項を追加します。
第〇〇条(作成費用の負担)
公正証書の作成に必要な手数料等の費用は、乙が負担するものとする。
あるいは
第〇〇条(作成費用の負担)
公正証書の作成に必要な手数料等の費用は、甲乙相等しい割合で負担する。
<公正証書作成する公証役場を定める例>
以下のような条項にします。
第一条(公正証書の作成)
甲および乙は、原契約について、原契約に基づいて発生する債務の履行につき、直ちに強制執行に服する旨の陳述(強制執行認諾文言)を記載した公正証書を○○公証役場で作成することに合意し、そのために必要な手続きを行う。
あるいは
第一条(公正証書の作成)
甲および乙は、原契約について、原契約に基づいて発生する債務の履行につき、直ちに強制執行に服する旨の陳述(強制執行認諾文言)を記載した公正証書を甲指定の公証役場で作成することに合意し、そのために必要な手続きを行う。
業務委託,業務請負に関する作成例
仕様変更、納期変更、金額変更に関する合意書,覚書
業務委託契約締結後、仕様の変更が発生した場合、記載する内容としては、
・いつ誰と誰が締結した契約についての仕様変更であるかを明示する(対象となる原契約を明確に)
・変更するに至った事情を明記する
・原契約の変更となる部分を明確に
・具体的な変更内容(原契約に別紙として仕様書などを添付している場合は、変更内容を変更仕様書として合意書,覚書に添付します)
・変更内容以外は原契約に定めるところとすることを確認して明記します
又、仕様変更に伴い納期や契約金額の変更が発生する場合は、その内容も明記します。
<仕様変更の記載例>
覚 書
委託者○○○○(以下「甲」という。)と受託者○○○○(以下「乙」という。)は、甲乙間の平成○○年○○月○○日付け業務委託契約書(以下「原契約」という。)に関して、次の理由により、以下の通り覚書(以下「本覚書」という。)を締結する。
「理由」
甲が依頼していた業務の仕様について変更の必要が生じた。
第一条(仕様の変更)
甲および乙は、原契約についての仕様書を以下とおり変更する。
【変更前】 原契約別紙仕様書
【変更後】 本覚書別紙変更仕様書
第二条(原契約維持)
甲及び乙は、本覚書に記載なき事項は、原契約に定めるところによることを確認する。
本覚書締結の証として、本覚書二通を作成し、甲乙相互に署名・押印のうえ各一通を保管することとする。
平成 年 月 日
甲 印
乙 印
仕様書は原契約に別紙として添付されている場合が多いことから、仕様の変更についても覚書に添付する形で変更することが多いです。仕様の変更に伴い納期の変更や費用負担を定める場合もあります。
<納期の変更>
第〇〇条(納期の変更)
甲及び乙は、原契約に定める契約期間を以下のとおり変更する。
【変更前】 平成○○年○○月○○日まで
【変更後】 平成○○年○○月○○日まで
<仕様変更に伴う費用について>
第〇〇条(追加費用の不請求)
乙は、甲に対し、本覚書による仕様変更に伴い発生する追加費用について請求しない。
本記載例は仕様変更に伴う追加費用について発生しないとする例です。
<金額の変更>
第〇〇条(契約金額の変更)
甲及び乙は、原契約における契約金額を以下のとおり変更する。
【変更前】 金〇〇〇円
【変更後】 金〇〇〇円
本記載例は契約金額全体の変更例ですが、仕様変更に伴う追加金額のみ定める場合は
第〇〇条(契約金額の追加)
甲は乙に対し、第〇〇条の仕様変更に伴い、原契約における契約金額に加え、追加の委託料として金〇〇円を支払う
―行政書士による”予防法務”―
日々の暮らしで役立つ法律文書作成のサポート
契約書,合意書,覚書,念書,和解書,借用書など、個人間でも法的書面化が必要とされる場面があります。「裁判までは考えていないけれど、口約束のままだと不安」、「後々もめたくない」、そんな時に役立つのが 行政書士による予防法務サービス です。暮らしの中の小さな取り決めを、安心の書面にして、未来のトラブルを防ぎます。行政書士として、客観的視点と法的観点から、冷静に整理・文書化いたします。当オフィスでは、合意書や念書,覚書,借用書,和解書,契約解除など、書類の作成サービスをリーズナブルな価格設定で提供しています。法的に整った書面をあなたの言葉から専門家が作成します。書き方の不安は不要です。
ご相談,お問い合わせ
契約書,合意書,覚書,念書,和解書,借用書など、個人間でも法的書面化が必要とされる場面があります。
行政書士として、客観的視点と法的観点から、冷静に整理・文書化いたします。
法的効力を備えた書面で、曖昧な約束を明確に。個人間トラブルを未然に防ぐ専門支援。
ご事情の整理から文案作成まで、丁寧に伴走します。
関連記事
契約書はじめ、合意書,念書,借用書,和解書などプライベートで役立つ法律文書関連記事

関連記事
有効な合意書や覚書の書き方
合意書や覚書は、基となる契約書に対して付随的・派生的・補足的な内容を記載するイメージがありますが、記載内容によっては契約書と同様に法的効果があります。合意者、覚書を作成するときの基本となる要点と無効とならない法的に有効な書き方について

関連記事
念書を書く場面とその効力や書き方
個人的なやり取りにおいて、約束した証拠として又は、事実を確認した証拠として交わされることが多い念書。念書に関して、作成する場面、契約書、合意書、覚書等の書類との違いや法的効力、書き方について。

関連記事
念書の具体的な作成例
念書の書き方として決まった書式とかはありません。「いつ何をして、どういう約束だったか」、「それがどうなったか」、「それでどうするのか」といったことを書きます。項目としては、「誰が誰に対して」、「どんな約束」、「いつ実行する」,「場所,方法,手段は」等です。
その他、よく読まれている記事

借用書は通常、借主側のみが署名,押印するのに対して、金銭消費貸借契約書は借主側,貸主側双方が署名,押印します。借用書や金銭消費貸借契約書を作成する場合、ポイントは、返す約束をしたこと、借主が金銭を受領済であることの明記です。

お金を貸した後から作成するのが債務承認弁済契約書と呼ばれる書類です。お金を貸すときに書類など作成せずに貸したけど、約束の時期になってもなかなか返してくれないなど、不安があるのであらためて書類を作成したいときに作成します。後から作成しても法的問題はありません。

業務委託契約の解除合意書はお互いが契約解除に合意したことを証明する書面です。法律上必ず作らなければならないというものではありません。また、作らなければ契約を解除できなというものでもありません。後のトラブル防止のため、話し合って合意した内容、特に清算条項を書面にします。

個人的なやり取りにおいて、約束した証拠として又は、事実を確認した証拠として交わされることが多い念書。念書に関して、作成する場面、契約書、合意書、覚書等の書類との違いや法的効力、書き方について。

和解契約書とは和解契約で合意した内容を書面にしたものです。書き方の基本は、「当事者」(誰と誰が),「日付」(いつ),「事実関係」(どんな争いがあって),「和解内容」(話し合いでどのように解決するか)です。和解契約とは、当事者双方が話し合いで互いに譲歩して、その間にある争いを止めることを約束する契約のことをいいます。

仮契約という言葉は広く一般的に使われています。ですが、何故「仮」であるのかを考えて、その効力をはっきりさせる必要があります。たとえタイトルに「仮」と記載されていても、その内容がお互いに何らかの義務を負う内容になっていれば、法的な効力を持つ契約書になります。

利用規約や同意書を作る時に検討する内容や書き方の手順について。WebサービスやWebアプリに限らず、自宅サロンや自宅教室など、ご自身が提供するサービスの利用規約や同意書といった書面を準備していますか?
権利義務書類,ビザ申請在留手続き書類,許認可申請書類などの書類作成

神戸 行政書士オフィス辻下
〒651-1145 兵庫県神戸市北区惣山町4丁目18ー7
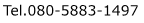 営業時間 10:00〜18:00(土・日・祝祭日 休)
営業時間 10:00〜18:00(土・日・祝祭日 休)
代表 行政書士 辻下仁雄
Profile
大学で応用数学を学び、システムエンジニアとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業し在に至る。
申請取次行政書士 2級ファイナンシャルプランニング技能士