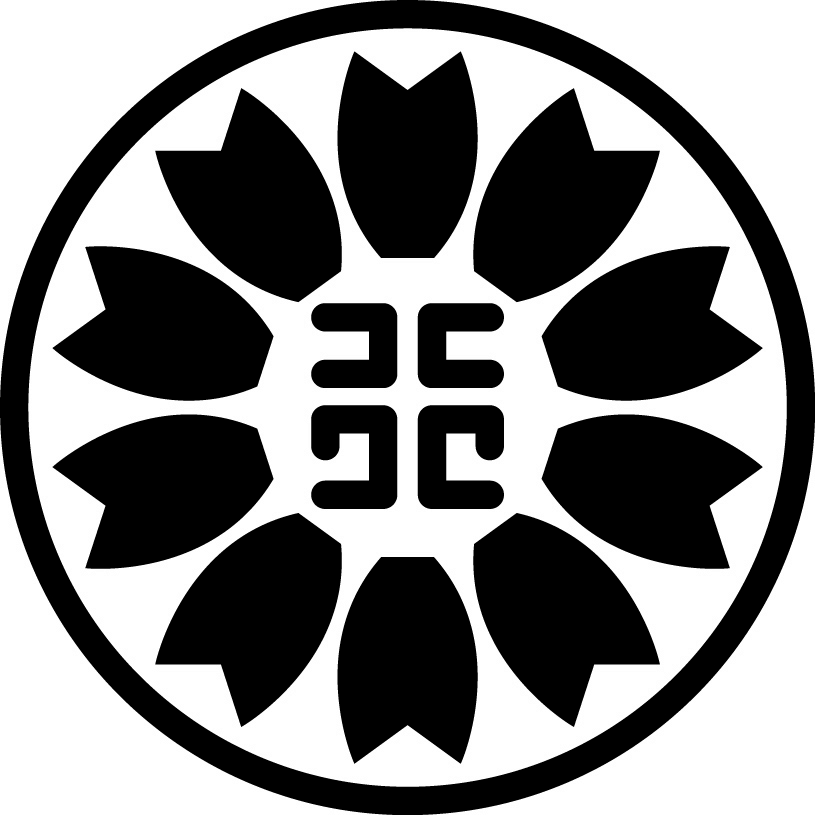行政書士による”予防法務”暮らしの安心書類作成を行政書士がサポートします
「裁判までは考えていないけれど、口約束のままだと不安」、「後々もめたくない」、そんな時に役立つのが 行政書士による予防法務サービス です。あなたの暮らしの中の小さな取り決めを、契約書,合意書,念書,覚書,借用書,和解書,契約解除など、安心の書面にして、未来のトラブルを防ぎます。まずは、無料のご相談をご利用ください。
お金の貸し借りによるトラブル防止
友人・知人・親族間でお金の貸し借りや立替がある方
書類を作成せず、口約束だけでお金の貸し借りがある方
借用書,念書,立替金清算覚書,債務承認弁済契約書(返済スケジュール表)、契約解除合意書など
日々の暮らしの取り決めをサポート
ルームシェアや共同生活,ペット譲渡,ご近所とのトラブル防止のための取り決めを検討している方
ルームシェ契約書,ペット譲渡契約書,利用ルール覚書,和解の合意書,念書,契約解除合意書など
家族・親族・ライフイベントをサポート
介護,財産管理,婚約・同棲など、家族・親族間の取り決めをしたい方
親の介護費用負担覚書,財産管理に関する合意書,婚約・同棲解消の合意書など
料金の目安
税込¥16,500〜
(詳細を伺った上でお見積り致します。)
シンプルな借用書,念書,覚書,合意書など書類1枚から承ります。
「自分の状況にどの書類が必要かわからない」といった場合でも、安心してご相談ください。個別に最適な書類をご提案いたします。
暮らしの中の小さな取り決めや口約束を、安心の書面にして、未来のトラブルを防ぎます。

行政書士による”予防法務”
行政書士だからできる3つの安心
- 法律に基づいた正確な書類作成
- 暮らしに合わせたオーダーメイド対応
- 予防法務でトラブルを未然に防止
・ 効力を持つ書面として残すことができます。
・ 状況に応じて柔軟に作成内容を調整します。
・ 事後対応ではなく「揉めない仕組みづくり」をサポートします。
予防法務は、日常を守る小さな備えです。行政書士が作成する一枚の書類が、あなたと大切な人の未来を守ります。
契約書,合意書,念書,覚書,借用書,和解書,契約解除合意書など、言った・言わないのトラブルを未然に防ぐ法的文書を、
個人間でもきちんと整えておきたい。そんな時は、当オフィスがお手伝いします。

個人間でも法的な書面が必要とされる場面があります。書面にした内容を読み返すことによって、お互いの認識のズレや内容の見落としを減らすことができます。当オフィスでは、お聞きした状況や背景を整理し、行政書士としての客観的視点と法的観点から冷静に当事者の権利義務を明文化します。

約束の当事者は誰か,いつ約束したか,いつからその約束の効力があるか,どんな権利と義務があってどんな場合に権利が発生し義務が発生するのか,その権利は誰のものでその義務はだれが負うのか,約束が守れなかったらどうするのか、等を法的に構成し、個人間の約束について紛争の抑止力となる(紛争予防の為の)書類、万一、紛争が起こった場合でも、当事者の行動規範となり紛争の円満解決の指針として機能するような書類作成を心がけております、
約束を「信頼できるカタチ」にするために、当オフィスが果たす3つの役割
―暮らしを守る予防法務―
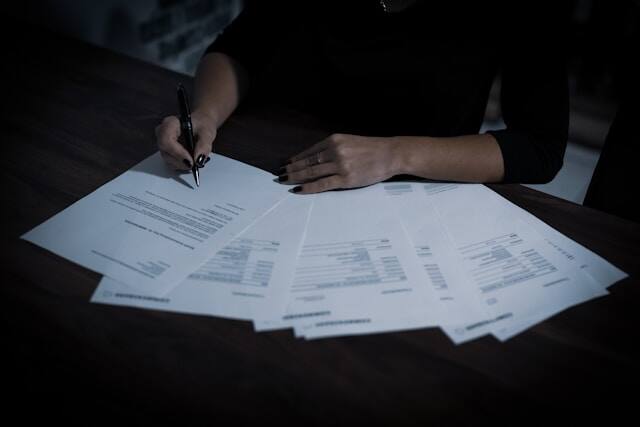
口約束を“安心のカタチ”に未然に争いを防ぐ「予防機能」。日常生活トラブルの芽を事前に摘み取る「予防機能」。日常生活で交わされる約束は、口頭のままでは誤解やトラブルのもとになります。行政書士が作成する契約書や覚書は、合意内容を明確に書面化。後々の「言った・言わない」を防ぎ、トラブルの芽を事前に摘み取ります。

利用者に合わせた「実務的・現実的な設計」。ご相談者の状況に合わせた“使える書類”実務的・現実的な設計。インターネットのテンプレートでは対応できない細かな事情や希望を反映できるのが行政書士の強み。必要な条項だけを整理し、不要なものを削ぎ落とした“実際に使える”書類を作成するため、当事者双方が納得しやすく、スムーズな合意形成に向けての第一歩です。

将来の法的対応につながる「証拠性・信頼性」。 万一の時にも備えられる“安心の証拠”証拠性・信頼性の確保。行政書士が関与して作成された書類は、裁判や調停の場で証拠として活用できる信頼性があります。また、必要に応じて「公正証書化」や「弁護士連携」に発展させることも可能。予防だけでなく、万一の時の安心にもつながる“暮らしのセーフティネット”となります。
ご利用の流れ
― 書類作成に関するお問い合わせ,ご相談からご依頼,完了まで ―

まずは、当ホームページのお問い合わせフォームで、状況をお聞かせください。「こんなこと相談していいのかな?」という段階でも大丈夫です。お気軽にお問い合わせください。営業時間 10:00〜18:00(土・日・祝祭日 休)
(お問い合わせフォームからは24時間受付)

ご相談内容を詳しく伺いながら、状況や背景を整理し、文書の種類を特定したうえで条件を整理します。費用が発生する場合は別途お見積り致します。その場でのご判断,ご返答は必要ございません。十分ご検討の上、ご連絡下さい。

ヒアリングしたご希望や背景を踏まえ、法的に有効かつ実用的な文案構成を設計します。初稿をご確認いただき、必要に応じて修正を加えながら、納得いただける内容に仕上げます。

完成した書類を納品いたします。
ご相談、お問い合わせ
その約束、大切だからこそ、形に残しませんか?まずは、状況をお聞かせください。
書面化が必要かどうか迷っている方も、お気軽にご相談ください。
行政書士が中立的な立場で、丁寧にお話を伺います。金銭の貸し借り・念書・和解書・合意書作成など、個人間の約束をサポート。
行政書士が、あなたの状況に合わせて最適な文書をご提案します。
お役立ち記事

借用書は通常、借主側のみが署名,押印するのに対して、金銭消費貸借契約書は借主側,貸主側双方が署名,押印します。借用書や金銭消費貸借契約書を作成する場合、ポイントは、返す約束をしたこと、借主が金銭を受領済であることの明記です。

契約解除の合意書を作成する場合としては、契約を解除することについて当事者双方が納得して合意していることを前提として作成されます。ですが、契約関係を明確にする意味でも、解除する契約の特定と清算条項をポイントとして書面を作成した方が後々のトラブルの防止になります。

お金を貸した後から作成するのが債務承認弁済契約書と呼ばれる書類です。お金を貸すときに書類など作成せずに貸したけど、約束の時期になってもなかなか返してくれないなど、不安があるのであらためて書類を作成したいときに作成します。後から作成しても法的問題はありません。

和解契約書とは和解契約で合意した内容を書面にしたものです。書き方の基本は、「当事者」(誰と誰が),「日付」(いつ),「事実関係」(どんな争いがあって),「和解内容」(話し合いでどのように解決するか)です。和解契約とは、当事者双方が話し合いで互いに譲歩して、その間にある争いを止めることを約束する契約のことをいいます。

個人的なやり取りにおいて、約束した証拠として又は、事実を確認した証拠として交わされることが多い念書。念書に関して、作成する場面、契約書、合意書、覚書等の書類との違いや法的効力、書き方について。
契約書・合意書・念書など書類のタイトルの違いと効力について
契約書のような権利義務に関する書類には色々なタイトルがあります。「契約書」,「合意書」,「和解書」,「同意書」,「覚書」,「念書」,「協議書」,「確認書」などですが、書類の持つ効力に基本的に違いはありません。その効力は書かれている内容によって判断します。また、書式も決まった形があるわけではなく自由です。つまり書かれている内容(本文)が当事者の関係や権利義務を規定し、表題(タイトル)は規定しません。とはいえ、タイトルを読めば、書いてある内容がイメージできるような実態を反映した具体的なものを付けるべきです。
契約書・合意書・念書など書類の存在意義
契約書や合意書,覚書、念書等の文書があるだけでは法的効力はありません。契約書や合意書,覚書、念書等の文書は当事者同士の合意事項(約束した内容)を記載した文書として存在しています。合意が本当にあったから記載内容の権利義務を有します。そもそも合意がなければ、いくら書類が存在しても権利や義務が発生することはありません。そこに記載されている内容の合意が本当にあったという事実を証明する証拠として作成されます。証拠としての効力を生ずるためには記載内容に不備があってはいけません。書類の存在やそのタイトルが法的効力の有無を決めるのではなく、その書類に書いてある内容(法律によって認められている権利や義務の生ずる内容)の事実が本当にあったのか無かったのかが法的効力の有無を決めます。
その書類、誰が書いた?―署名の重要性―
厳密には”誰が書いた”かは重要ではなく、”誰の意思に基づいて書かれているか”が重要になります。もちろん自筆で書かれていれば、書いた本人の意思に基づいて書かれていると推定されます。自筆ではなくタイプ打ちの書類の場合は、署名があれば署名した本人の意思に基づいて書かれていると推定されます。通常、タイプ打ちの書類を作成するので、自筆の署名が重要になります。誰が作成したか解らない書類であっても、そこに自筆の署名があれば、署名した本人の意思に基づいていると推定されます。ただし、「推定」されるのであって、反対の証拠があれば、この推定は否定されます。
About Us
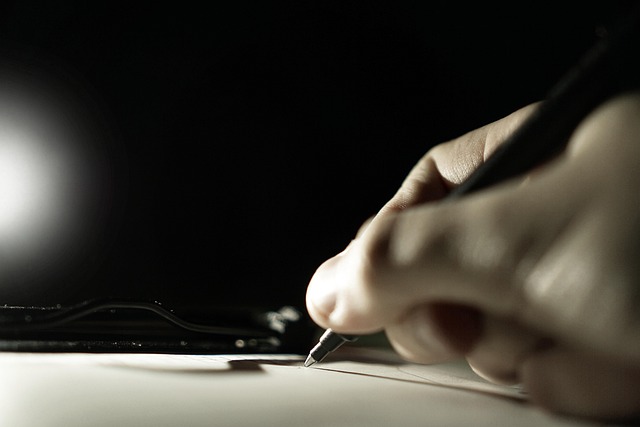
行政書士 辻下仁雄
大学で応用数学を学びSEとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業、現在に至る。
神戸市で行政書士事務所を開設している行政書士オフィス辻下の辻下仁雄です。論理的な構成と実務的で説得力ある書類作成を心がけております。ご依頼者一人ひとりに合わせたオーダーメイド対応で画一的なテンプレートではなく個別最適化された書類をご提案致します。細やかな条件がからむ案件でもご相談ください。
権利義務書類,ビザ申請在留手続き書類,許認可申請書類などの書類作成
スマホ版ホームページアクセス


神戸 行政書士オフィス辻下
〒651-1145 兵庫県神戸市北区惣山町4丁目18ー7
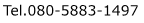 営業時間 10:00〜18:00(土・日・祝祭日 休)
営業時間 10:00〜18:00(土・日・祝祭日 休)
代表 行政書士 辻下仁雄
Profile
大学で応用数学を学び、システムエンジニアとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業し現在に至る。
申請取次行政書士 2級ファイナンシャルプランニング技能士