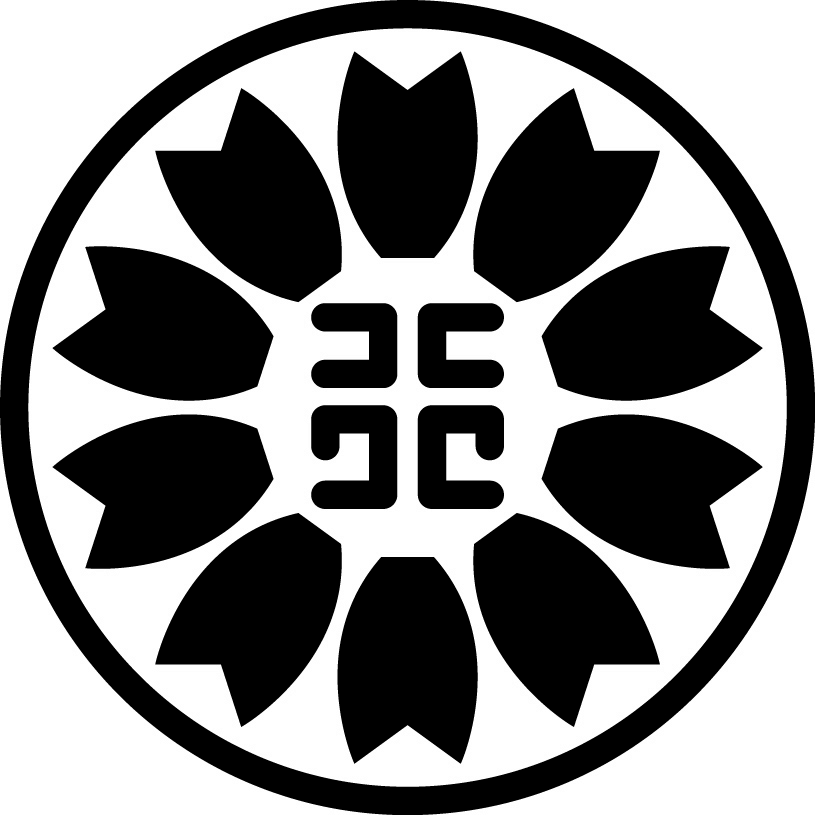プライベートで役立つ法律文書契約解除(解約)合意書の書き方と作成する時のポイント
契約解除の合意書
契約を解除することについて当事者双方が納得して合意していることを前提として、契約解除合意書のような書面を作成します。先に締結している契約で定められた解除事由に該当した場合や、契約違反があった場合など、一般的な意味での解除の場合は、解除する当事者の一方的な意思表示によって行い、相手方の同意は不要です。が、合意解除の場合は、あくまでも契約当事者双方の合意を前提としています。双方納得して契約を解除しますが、契約関係を明確にする意味でもこのような書面を作成した方が後々のトラブルの防止になります。
契約書や念書,合意書,借用書などの権利義務書類について、疑問点・不明点等あれば、お問い合わせください。
書き方と作成時の基本となるポイント
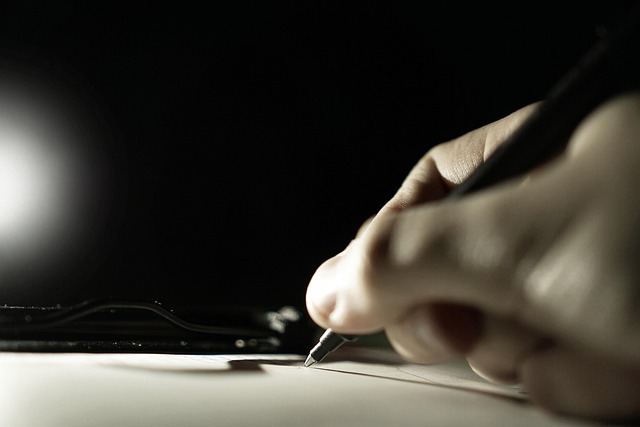
契約解除の合意書は、あくまでも契約当事者の合意を前提として作成するので、解除合意に至るまでに何らかの話し合いがもたれていることが通常です。平たく言えば、その話し合いの中でお互い取り決めたことを書面にすれば問題はありません。が、基本となるポイントは以下のような内容です。
- 解除する契約の特定
- 解除日
- 原状回復義務の内容
- 清算条項
1.解除する契約の特定
解除することに合意した契約がどの契約かを特定することです。通常は先行契約の「締結日」と「契約名」で特定します。折角、話し合って合意してもどの契約を解除したのかが曖昧であれば、後々のトラブルの原因になります。例えば、
○○○○(以下、「甲」という。)と○○○○(以下、「乙」という。)は、甲乙間で締結した○○年○○月○○日付「○○○○契約」(以下、「原契約」という。)に関して、解除することに合意し、以下のとおり合意書(以下、「本合意書」という。)を締結する。
又、原契約を全部解除するのではなく、原契約の一部のみを解除する場合は、解除の対象となるのは原契約のどの部分であるのかを特定するようにします。そのうえで、原契約を維持する条項を記載します。
第○○条(原契約維持)
甲及び乙は、本合意書に記載なき事項は、原契約の定めるところによることを確認する。
2.解除日
いつ契約の効力を無くすのかを明記します。
「○○年○○月○○日付」のように日付を明記する場合や、「本合意書締結日」のように記載します。
3.原状回復の内容
解除によって契約当事者はお互い契約が無かった状態に戻すため、契約に基づいて受けた給付を相手方に返還する義務を負います(原状回復義務)。その返還するもの、例えば、金銭や財物などを特定し、いつまでにどういった方法で返還するかを記載します。もちろん、相互の合意が前提なので、話し合って「お互い何も返還するものはありません。」という合意に至れば、記載しないのではなく、何もない旨を記載します。例えば代金の返還がある場合、
第○○条(代金の返還)
甲は、原契約の解除に伴い、受領済の代金〇〇円を○○年○○月○○日限り、乙が指定する金融機関口座に振り込む方法により返還する(振込手数料は甲負担)。
お互い何も返還するものがない場合、簡易な例ですが、
第○○条(放棄条項)
甲及び乙は、相手方に対するその余の請求をそれぞれ放棄する。
4.清算条項
上記の原状回復の内容とも関係しますが、契約解除によって返還すべきものの返還が済んだ後あるいは、そもそも返還すべきものが無い場合など、お互い債権債務はありません(相手方に何か請求する権利も、相手から請求を受ける義務もありません)ということを確認する清算条項です。標準的な例として、
第○○条(清算条項)
甲及び乙は、相手方に対するその余の請求をそれぞれ放棄し、本合意書に定めるほか、何らの債権債務が無いことを相互に確認する。
5.その他
上記の内容以外にも、解除の対象となる原契約の内容によっては、契約終了後も引き続きその効力を維持するような、いわゆる残存条項が定められていることもあります。その場合は、「解除後の効力はどうするのか?」又、原契約に契約の解除ができる条件等が記載されており、「そもそも解除ができるのか?」ということもありますが、そういったことも含めて検討済みとして、あくまでも、契約当事者同士が話し合って「無かったことにしましょう」という合意を前提として合意書を作成します。当事者全員が合意(納得)すれば、締結済み契約を解除する新たな契約を締結したことになり、契約自由(私的自治の原則)によって認められています。
契約解除合意書の作成例
標準的な例
○○○○(以下、「甲」という。)と○○○〇(以下、「乙」という。)は、甲乙間で締結した○○年○○月○○日付「△△△△契約」(以下、「原契約」という。)に関して、以下のとおり合意したので、合意書(以下、「本合意書」という。)を締結する。
第1条
甲及び乙は、□□年□□月□□日(以下、「解除日」という。)をもって原契約を合意解除することとし、解除日以降、原契約はその効力を失うことを相互に確認する。
第2条
甲及び乙は、相手方に対するその余の請求をそれぞれ放棄し、本合意書に定めるほか、何らの債権債務がないことを確認する。
以上、本合意書締結の証として、本合意書2通を作成のうえ、甲乙相互に署名又は記名,押印のうえ、各1通を保管するものとする。
○○年○○月○○日
甲 印
乙 印
金銭の返還を伴う例
○○○○(以下、「甲」という。)と○○○〇(以下、「乙」という。)は、甲乙間で締結した○○年○○月○○日付「△△△△契約」(以下、「原契約」という。)に関して、以下のとおり合意したので、合意書(以下、「本合意書」という。)を締結する。
第1条
甲及び乙は、□□年□□月□□日(以下、「解除日」という。)をもって原契約を合意解除することとし、解除日以降、原契約はその効力を失うことを相互に確認する。
第2条
甲は原契約の解除に伴い、受領済の代金○○円を乙に返還し、乙はこれを受領した。
第3条
甲及び乙は、相手方に対するその余の請求をそれぞれ放棄し、本合意書に定めるほか、何らの債権債務がないことを確認する。
以上、本合意書締結の証として、本合意書2通を作成のうえ、甲乙相互に署名又は記名,押印のうえ、各1通を保管するものとする。
○○年○○月○○日
甲 印
乙 印
上記は、原契約として売買契約を想定した例ですが、前文で解除する原契約を特定し、第1条で解除する日付を規定しています。又、原状回復として第2条で受領済金銭の返還を規定し、第3条で清算条項を規定しています。売買契約の目的物が引渡し済であれば、受領済目的物を返還する必要があります。例えば、以下のような条項を追記します。
第○○条
乙は○○年○○月○○日、本件受領物を甲に返還するものとする。
契約の解除は、話し合いに基づく合意を前提とした解除にしましょう。合意後は、無用なトラブルを避けるためにも書面を作成することを心がけましょう。
―行政書士による”予防法務”―
日々の暮らしで役立つ法律文書の作成サポート
契約解除合意書の作成サービスのご案内
契約解除に必要な「合意書」の文案設計・作成代行を承っております。専門家として、法令上の視点と当事者間の状況を踏まえ、目的に合致した適正な書面化を支援いたします。「書き方はなんとなくわかったけど、実際の文書の構成や文言の選び方」に迷っている方、契約解除には、中立的な文言選定が必要です。ご相談者様の状況に合わせ、法的観点から最適な文案を設計し、ご事情に応じて、契約解除に必要な文言を一緒に整理するところから始めます。
- ヒアリングをもとに構成をご提案
- 文案ドラフトを提示
- 修正・完成・納品まで一括対応(PDF/紙面/郵送対応)
サービス内容の詳細は「契約解除合意書の作成サービス」を参照ください。
ご相談,お問い合わせ
契約書,合意書,覚書,念書,和解書,借用書など、個人間でも法的書面化が必要とされる場面があります。
行政書士として、客観的視点と法的観点から、冷静に整理・文書化いたします。
法的効力を備えた書面で、曖昧な約束を明確に。個人間トラブルを未然に防ぐ専門支援。
ご事情の整理から文案作成まで、丁寧に伴走します。
関連記事
契約書はじめ、合意書,念書,借用書,和解書などプライベートで役立つ法律文書関連記事

関連記事
契約や合意(約束)をやめたい
一旦契約を締結すると、契約の当事者はその内容を守る義務を負います。原則、契約書や合意書等の書類が「有る」とか「無い」とかは関係なく、一方的にやめることはできません。ただ相手方が「そう言うのなら無かったことにしましょう」等と同意してくれる場合は別です。

関連記事
有効な合意書や覚書の書き方
合意書や覚書は、基となる契約書に対して付随的・派生的・補足的な内容を記載するイメージがありますが、記載内容によっては契約書と同様に法的効果があります。合意者、覚書を作成するときの基本となる要点と無効とならない法的に有効な書き方について

関連記事
合意書や覚書の具体的な作成例
建物賃貸借,金銭消費貸借,業務委託,業務請負に関するものなど、合意書や覚書の記載内容の具体的例や作成のポイント
その他、よく読まれている記事

借用書は通常、借主側のみが署名,押印するのに対して、金銭消費貸借契約書は借主側,貸主側双方が署名,押印します。借用書や金銭消費貸借契約書を作成する場合、ポイントは、返す約束をしたこと、借主が金銭を受領済であることの明記です。

お金を貸した後から作成するのが債務承認弁済契約書と呼ばれる書類です。お金を貸すときに書類など作成せずに貸したけど、約束の時期になってもなかなか返してくれないなど、不安があるのであらためて書類を作成したいときに作成します。後から作成しても法的問題はありません。

業務委託契約の解除合意書はお互いが契約解除に合意したことを証明する書面です。法律上必ず作らなければならないというものではありません。また、作らなければ契約を解除できなというものでもありません。後のトラブル防止のため、話し合って合意した内容、特に清算条項を書面にします。

個人的なやり取りにおいて、約束した証拠として又は、事実を確認した証拠として交わされることが多い念書。念書に関して、作成する場面、契約書、合意書、覚書等の書類との違いや法的効力、書き方について。

和解契約書とは和解契約で合意した内容を書面にしたものです。書き方の基本は、「当事者」(誰と誰が),「日付」(いつ),「事実関係」(どんな争いがあって),「和解内容」(話し合いでどのように解決するか)です。和解契約とは、当事者双方が話し合いで互いに譲歩して、その間にある争いを止めることを約束する契約のことをいいます。

仮契約という言葉は広く一般的に使われています。ですが、何故「仮」であるのかを考えて、その効力をはっきりさせる必要があります。たとえタイトルに「仮」と記載されていても、その内容がお互いに何らかの義務を負う内容になっていれば、法的な効力を持つ契約書になります。

利用規約や同意書を作る時に検討する内容や書き方の手順について。WebサービスやWebアプリに限らず、自宅サロンや自宅教室など、ご自身が提供するサービスの利用規約や同意書といった書面を準備していますか?
権利義務書類,ビザ申請在留手続き書類,許認可申請書類などの書類作成

神戸 行政書士オフィス辻下
〒651-1145 兵庫県神戸市北区惣山町4丁目18ー7
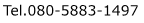 営業時間 10:00〜18:00(土・日・祝祭日 休)
営業時間 10:00〜18:00(土・日・祝祭日 休)
代表 行政書士 辻下仁雄
Profile
大学で応用数学を学び、システムエンジニアとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業し在に至る。
申請取次行政書士 2級ファイナンシャルプランニング技能士