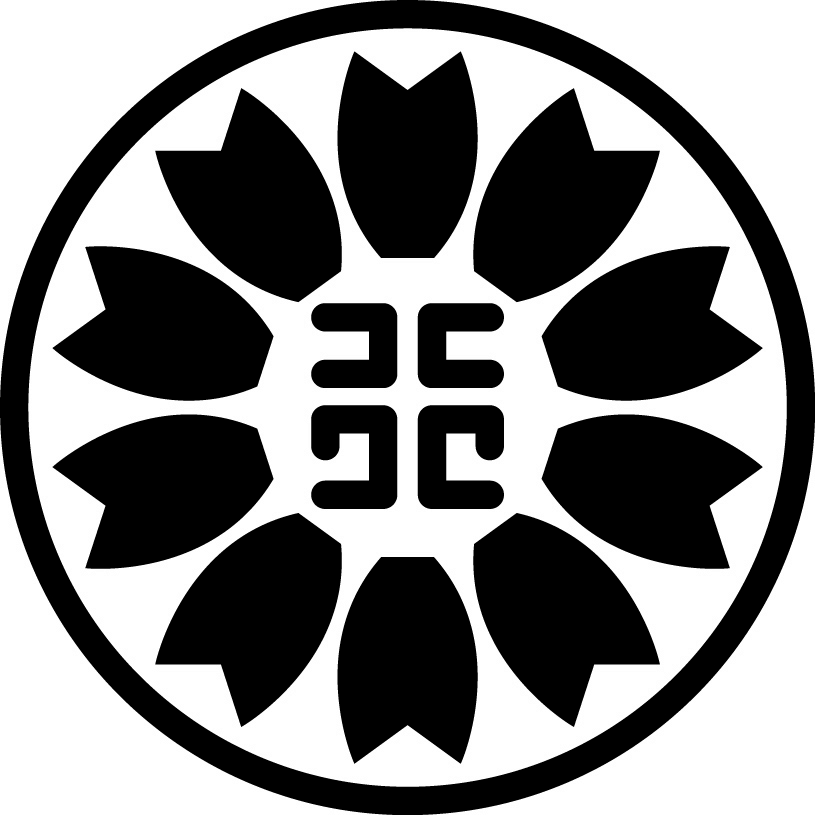プライベートで役立つ法律文書契約や合意(約束)をやめたい
日々の暮らしで役立つ法律文書

契約の無効
専門家が書類を作成する場合、無効とならない書類の作成を心掛けています。契約書や合意書等の書類について、「無効にならないかなぁ」といったお話を聞くことがありますが、一方的に「無効にしたい」つまり、「最初からなかったことにしたい」というようなことは、簡単にはできません。
契約書や念書,合意書,借用書などの権利義務書類について、疑問点・不明点等あれば、お問い合わせください。
契約や合意の解除や取消し,無効について
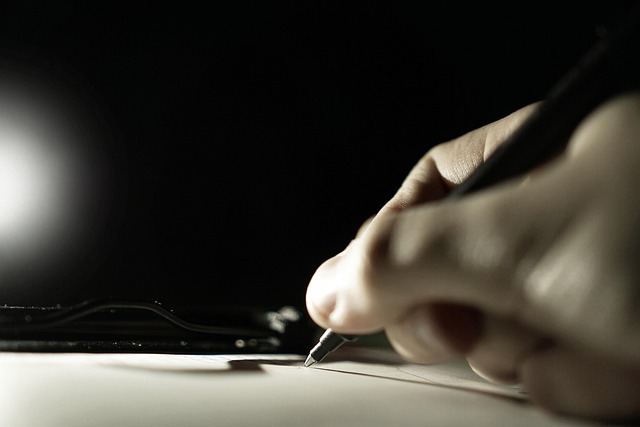
一旦契約を締結すると(約束すると)、その契約の当事者はその契約に拘束され、その内容を守る義務を負います。原則、契約書や合意書等の書類が「有る」とか「無い」とかは関係ありません。後から、「やっぱり気が変わった」、「やっぱりちょっと納得できない」等の理由で一方的にやめることはできません。もちろん契約の相手方が「そんなに言うのなら無かったことにしましょう」、「それならそういうことにしましょう」と同意してくれる場合は別です。「一旦有効に成立した契約を無かったことにする」という新しい別の契約(合意)が成立したということになります。
そもそも無効とは
「無効」とはそんな約束は初めから存在していません。言葉をかえて言うと、契約の効果は最初から全く生じていなかったということです。初めから存在していないのだから、いつまでたっても無いままです。時間が過ぎても有効になることはありません。存在していないものを取消す(解除する)こともできません、無効にすることもできません。当事者が有効にしても良いと思っても有効にできません。
無効と取消し
「無効」とは初めから効力のある契約(約束)は、成立していない(そんな約束は存在していません)ということです。上で記述しているような「一旦有効に成立した契約を無かったことにする」ということは、契約自体は有効に成立したが、当事者同士の話し合いで無かったことにします。ということで、「無効」ではなく「有効な契約」をお互いが合意して取消す(解除する)ということになります。一方的に「無効にしたい」つまり、「最初からなかったことにしたい」ということは、言葉を変えて言うとすれば、「有効に成立した契約を取消し(解除し)たい」ということです。(虚偽表示や錯誤を理由として無効を主張する場合もあります。)
契約や合意を取消したい
上記の無効の欄でも記述しましたが、「契約したけど、やっぱりやめたい」ということは、「無効にする」ということではなく、「有効に成立した契約」を後から取消す(解除する)ということです。
そもそも取消とは
いったん有効に成立した契約や合意を、取消すことができる当事者が取消すことができるということです。取消をしなければ、契約は有効なまま継続します。取消した場合は、契約は最初に遡って無かったことになります。最初から無かったことになるという点では無効と同じです。ただ、いつでも誰でも取消すことができるのであれば、契約自体、あまり意味がないようになってしまいます。なので、取消しができる場合というのが限られています。
取消しできる場合とは
未成年者や成年被後見人、被保佐人などの制限行為能力者が単独でした契約です。(制限行為能力者が単独でした契約でも取消しができない場合もあります。)次に、詐欺や強迫によってした契約です。(その他、消費者契約法、特定商取引法にも取消し制度があります。)取消しができる場合でも、「いったんは有効に成立しています。ただし取消すことができます。」という状態が続けば、契約の当事者は不安定な状態が続きます(いつ取消されるのかはっきりしない)。そこで、取消しができる場合でも、取消しができる期間が制限されています。その期間がすぎれば、完全に有効な契約として成立し、取消すことができなくなります。
将来に向かって契約解除(解約)
契約を解除した場合、契約の最初に戻って「契約は無かったことにします」ということですが、一回きりの契約、例えば売買契約などは無かったことにできますが、契約の中には一定期間継続して行われるものもあります。代表的な例としては雇用契約や建物賃貸借契約などです。このような契約では解除によって最初から無かったことにした場合、既に履行された部分も無かったことにしますといったとき不都合が生じます。そのため、このような契約解除の場合は、契約を解除した時から将来に向かって契約の効力を無くすということになります。一般的には解約と言われますが、厳密に解除と解約を区別しているようでもありません、ほとんど同じ意味と考えて問題ありません。
契約をやっぱりやめたい
「無効となる」、「取消すことができる」という契約は限られています。無効原因もなく、取消し原因もない契約は有効に成立します。いったん有効に成立した契約は簡単には無かったことにはできません。契約当事者が話し合って、「無かったことにしましょう」という合意が得られれば、「無かったことにする」という新しい契約を締結することになります。あるいは、契約内容に「こういった条件が整えば、この契約は無かったことにします。」とうい内容を盛り込んでおく。その場合でもその条件が成立しない状態で、一方的に「やめます」は簡単ではありません。
合意解除について
完全に有効に成立した契約(無効となる原因がなく、取消し原因もない契約)であっても、解消することができる場合があります。そのような場合を契約の解除といいます。このページの最初の方でも記述しましたが、契約当事者同士が話し合って「無かったことにしましょう」と合意すれば、それでやめること(契約の解除)ができます。当事者全員が合意(納得)すれば、解除する契約を新たに締結したことになります。契約自由(私的自治の原則)によって認められています。
契約を解除することについて当事者双方が納得して合意していることを前提として、契約解除合意書のような書面を作成します。双方納得して契約を解除しますが、契約関係を明確にする意味でもこのような書面を作成した方が後々のトラブルの防止になります。
その他
それ以外には、上でも記述しましたが、契約を締結するときに、やめる(解除する)条件を決めておき、その条件が整えば解除できます。ただしその条件が当事者間においてあまりにも不公平であれば解除が認められない場合もあります。以上の2つは当事者同士の話し合いで(契約の内容を話し合うことも含めて)決めることができます。あと一つは、当事者同士の話し合いに関係なく、法律の規定により解除できる場合があります。法律の規定による解除で典型的なものは、契約の中で決めていた約束を守れなかった場合(債務不履行)です。「約束の期限になっても何もしてくれない。だから催促したけどやっぱり何もしてくれない。」あるいは、「期限はまだ来ていないけど、既に約束を守れなくなった」といった場合です(いづれの場合も約束を実行する側に責任があるということが必要ですが)。契約が解除されると、約束する前の状態に戻ります。つまり、「そんな約束はありませんでした。」ということになります。
いづれにせよ、一旦約束が成立した場合、「やっぱりやめた」は簡単ではありません。契約書や合意書等に署名する場合は、内容をよく確認してから署名することを心掛けましょう。
契約を解除するのであれば、極力当事者同士で話し合って合意による解除を心がけましょう。また、解除の合意に至った場合は、合意書を作成するようにしましょう。
ご相談,お問い合わせ
契約書,合意書,覚書,念書,和解書,借用書など、個人間でも法的書面化が必要とされる場面があります。
行政書士として、客観的視点と法的観点から、冷静に整理・文書化いたします。
関連記事
契約書はじめ、合意書,念書,借用書,和解書などプライベートで役立つ法律文書関連記事

関連記事
和解契約書(和解の合意書)の書き方
和解契約書とは和解契約で合意した内容を書面にしたものです。書き方の基本は、誰と誰が,いつ,どんな争いがあって,話し合いでどのように解決するか、です。和解契約とは、当事者双方が話し合いで互いに譲歩して、その間にある争いを止めることを約束する契約のことをいいます。

関連記事
契約解除合意書の書き方とポイント
解除することについて当事者双方が納得して合意していることを前提として作成されます。ですが、契約関係を明確にする意味でも、解除する契約の特定と清算条項をポイントとして書面を作成した方が後々のトラブルの防止になります。

関連記事
有効な合意書や覚書の書き方
合意書や覚書は、基となる契約書に対して付随的・派生的・補足的な内容を記載するイメージがありますが、記載内容によっては契約書と同様に法的効果があります。合意者、覚書を作成するときの基本となる要点と無効とならない法的に有効な書き方について
その他、よく読まれている記事

借用書は通常、借主側のみが署名,押印するのに対して、金銭消費貸借契約書は借主側,貸主側双方が署名,押印します。借用書や金銭消費貸借契約書を作成する場合、ポイントは、返す約束をしたこと、借主が金銭を受領済であることの明記です。

お金を貸した後から作成するのが債務承認弁済契約書と呼ばれる書類です。お金を貸すときに書類など作成せずに貸したけど、約束の時期になってもなかなか返してくれないなど、不安があるのであらためて書類を作成したいときに作成します。後から作成しても法的問題はありません。

業務委託契約の解除合意書はお互いが契約解除に合意したことを証明する書面です。法律上必ず作らなければならないというものではありません。また、作らなければ契約を解除できなというものでもありません。後のトラブル防止のため、話し合って合意した内容、特に清算条項を書面にします。

個人的なやり取りにおいて、約束した証拠として又は、事実を確認した証拠として交わされることが多い念書。念書に関して、作成する場面、契約書、合意書、覚書等の書類との違いや法的効力、書き方について。

和解契約書とは和解契約で合意した内容を書面にしたものです。書き方の基本は、「当事者」(誰と誰が),「日付」(いつ),「事実関係」(どんな争いがあって),「和解内容」(話し合いでどのように解決するか)です。和解契約とは、当事者双方が話し合いで互いに譲歩して、その間にある争いを止めることを約束する契約のことをいいます。

仮契約という言葉は広く一般的に使われています。ですが、何故「仮」であるのかを考えて、その効力をはっきりさせる必要があります。たとえタイトルに「仮」と記載されていても、その内容がお互いに何らかの義務を負う内容になっていれば、法的な効力を持つ契約書になります。

利用規約や同意書を作る時に検討する内容や書き方の手順について。WebサービスやWebアプリに限らず、自宅サロンや自宅教室など、ご自身が提供するサービスの利用規約や同意書といった書面を準備していますか?
権利義務書類,ビザ申請在留手続き書類,許認可申請書類などの書類作成

神戸 行政書士オフィス辻下
〒651-1145 兵庫県神戸市北区惣山町4丁目18ー7
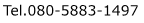 営業時間 10:00〜18:00(土・日・祝祭日 休)
営業時間 10:00〜18:00(土・日・祝祭日 休)
代表 行政書士 辻下仁雄
Profile
大学で応用数学を学び、システムエンジニアとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業し在に至る。
申請取次行政書士 2級ファイナンシャルプランニング技能士