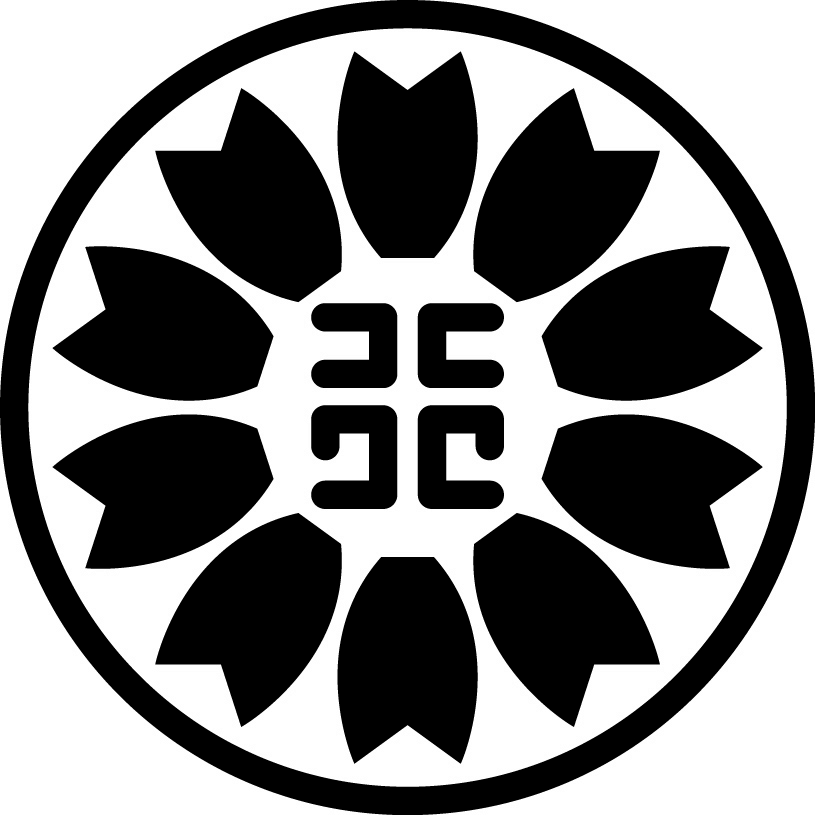日々の暮らしで役立つ法律文書お金を貸した後から作成する債務承認弁済契約書
債務承認弁済契約書
友人,知人などプライベートな間での貸し借りのときは文書を作らずに貸し借りを行うこともあり、そのため後々トラブルとなる事はよくあります。金銭の貸し借りの約束は、契約そのものが単純なのでメモ書き一枚でも効力を有することもあります。そのメモを原契約として後から作成できる契約書が債務承認弁済契約書です。
契約書や念書,合意書,借用書などの権利義務書類について、疑問点・不明点等あれば、お問い合わせください。
お金の貸し借りがあった後から書類を作成
お金の貸し借りは文書が無くても口約束だけで成立(金銭消費貸借契約が成立)するので、友人,知人など個人間の貸し借りのときは文書を作らずに貸し借りを行うこともあり、そのため後々トラブルとなる事例はよくあります。何も文書を残していないといった場合でも、借主の協力で後から書類を作成することはできます、法的問題もありません。また、売買の代金をまだ支払ってもらっていない、立て替え代金をまだ支払ってもらっていない、何度か金銭を貸したけど返してもらっていないなど、複数の貸し借りを一つのお金の貸し借りとして文書をまとめて作成することも可能です。「債務承認弁済契約書」と「(金銭)準消費貸借契約書」です。
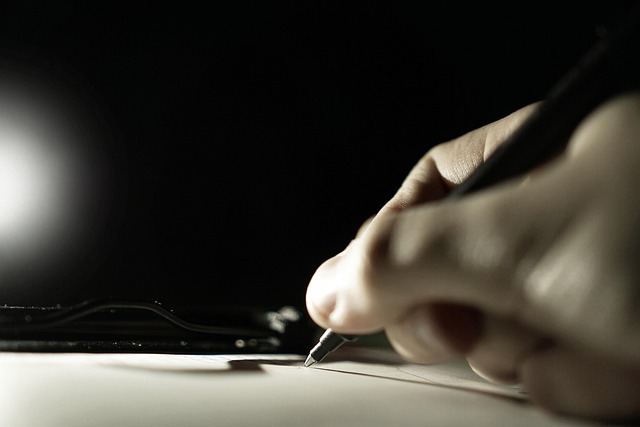
債務承認弁済契約書
借用書や金銭消費貸借契約書はお金の貸し借り時に作成するのに対して、お金を貸した後から作成するのが債務承認弁済契約書と呼ばれる文書です。後から作成しても法的問題もありません。お金を貸すときに文書など作成せずに貸したけど、約束の時期になってもなかなか返してくれないなど、不安があるのであらためて文書を作成したいといったときに作成します。ポイントは、「借主が確かに○○円のお金を借りていて返す義務があります。」ということを認めてもらい、そのことを文言として明記することです。そのためには、借主の協力が必要です。借主と話し合い、文書を作ることを条件に返済期間の延長や支払い方法の変更(分割払いOK)等、貸主側が譲歩することも検討し、最終的に取り決めた内容を文書にします。取り決めの要点は以下のような内容です。
- 貸付金元金の額
- 返済時期
- 利息の有無と利息を付ける場合の利率
- 遅延損害金
- 期限の利益を失う条件
一番大事な「返済義務を認めてもらう」ことですが、冒頭でも書きましたが、たった一行のメモ書きが効力を有します。そのメモ書きを原契約として、債務承認弁済契約書や借入金に関する覚書,借入金支払いに関する覚書,念書などを後から作成することができます。
債務承認弁済契約書の作成例
大切なポイントは返済すべき借入金があることを承認してもらい、これをどのようにして支払うかを記載します。
債務承認弁済契約書
□□□□を甲、○○○○を乙として、以下のとおり、債務弁済契約を締結する。
第1条(債務の承認)
乙は甲に対し、○○年○○月○○日現在、未払い借入金□□□円の債務を負っていることを承認し、以下の条項に従い弁済することを約した。
第2条(弁済方法)
乙は甲に対し、前条の借入金について、以下のとおり甲の指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払うこととする。ただし、振込にかかる手数料は乙の負担とする。
1 ○○年○○月から○○年○○月まで毎月末日限り金□□円
○○○○年○○月○○日
甲)
住所
氏名 印
乙)
住所
氏名 印
利息を付ける場合は、例えば
利息は年○○%とし、毎月末日限りその月分を支払う。
期限の利益喪失条項を付ける場合は、例えば
乙が第2条の分割金の支払を○○回以上怠った場合には、甲からの通知催告がなくとも当然に期限の利益を喪失する。
遅延損害金を付ける場合は、例えば
期限後又は、期限の利益を喪失ときは、以降完済にいたるまで年○○%の遅延損害金を付して支払う。
等を追記します。
準消費貸借契約書
「準消費貸借契約書」という文書があります。何度もお金を貸していて、少しは返してもらったけど、まだ返してもらっていない貸金があるといった場合、数口の貸金を1口の金銭消費貸借にまとめる目的で約束しなおす。あるいは、売買代金の支払いや、仕事(請負報酬)の代金をまだ支払ってもらっていない場合、その支払代金を、お金を貸していることにして金銭消費貸借として約束しなおすということです。
金銭消費貸借ではお金を渡すことが必要ですが、準消費貸借ではお金の授受は必要とされていません。当事者の合意だけで成立します。また、成立には書面は必要ではありませんが、作成した方が良いことに変わりはありません。支払期限の延期,あるいは支払いの一部免除などを条件として相手方に話し合いに応じてもらい文書を作成ます。また、保証人を立ててもらう、あるいは執行認諾約款付公正証書を作成するといった約束を加えて、あらためて文書を作成します。
取り決めの要点は、上記の債務承認弁済契約書と同様ですが、重要なことは準消費貸借の場合には、その基本となった債務(貸しているお金,売買代金が未払い,仕事の報酬が未払い等)が有効に成立していることです。基本となった債務が成立していなければ準消費貸借も無効となります。
したがって既存の債務がどのようなものかを特定しておくことが重要です。そして、その既存の債務をしっかりと文書に明記しておくことです。
―行政書士による”予防法務”―
日々の暮らしで役立つ法律文書作成のサポート
契約書,合意書,覚書,念書,和解書,借用書など、個人間でも法的書面化が必要とされる場面があります。「裁判までは考えていないけれど、口約束のままだと不安」、「後々もめたくない」、そんな時に役立つのが 行政書士による予防法務サービス です。暮らしの中の小さな取り決めを、安心の書面にして、未来のトラブルを防ぎます。行政書士として、客観的視点と法的観点から、冷静に整理・文書化いたします。当オフィスでは、合意書や念書,覚書,借用書,和解書,契約解除など、書類の作成サービスをリーズナブルな価格設定で提供しています。法的に整った書面をあなたの言葉から専門家が作成します。書き方の不安は不要です。
債務承認契約書や借用書など、金銭トラブルを防ぐ書類を専門家が作成
「書類なしでお金を貸してしまった…」、「これからお金を貸すけど…」、債務承認弁済契約書?金銭消費貸借契約書?借用書?どれを作ればいいかわからない方へ。お金を貸した後からでも作成できる金銭貸借に関する正式な書類を、専門家がわかりやすくサポートします。
個人間の貸し借りも安心に。今からでも作れる借用書・念書・債務承認契約書で、金銭トラブルを未然に防ぎましょう。一人ひとりにの状況に合わせて個別最適化された書類をご提案,作成致します。
サービス内容の詳細は『弁済契約書や借用書などの書類作成サービス』を参照ください。
ご相談,お問い合わせ
契約書,合意書,覚書,念書,和解書,借用書など、個人間でも法的書面化が必要とされる場面があります。
行政書士として、客観的視点と法的観点から、冷静に整理・文書化いたします。
法的効力を備えた書面で、曖昧な約束を明確に。個人間トラブルを未然に防ぐ専門支援。
ご事情の整理から文案作成まで、丁寧に伴走します。
プライベートで役立つ法律文書関連記事
契約書はじめ、合意書,念書,借用書,和解書など

関連記事
借用書など金銭貸借に関する契約書等の書き方
借用書は通常、借主側のみが署名,押印するのに対して、金銭消費貸借契約書は借主側,貸主側双方が署名,押印します。借用書や金銭消費貸借契約書を作成する場合、ポイントは、返す約束をしたこと、借主が金銭を受領済であることの明記です。

関連記事
和解契約書(和解の合意書)の書き方
和解契約書とは和解契約で合意した内容を書面にしたものです。書き方の基本は、誰と誰が,いつ,どんな争いがあって,話し合いでどのように解決するか、です。和解契約とは、当事者双方が話し合いで互いに譲歩して、その間にある争いを止めることを約束する契約のことをいいます。

関連記事
契約解除合意書の書き方とポイント
解除することについて当事者双方が納得して合意していることを前提として作成されます。ですが、契約関係を明確にする意味でも、解除する契約の特定と清算条項をポイントとして書面を作成した方が後々のトラブルの防止になります。
その他、よく読まれている記事

借用書は通常、借主側のみが署名,押印するのに対して、金銭消費貸借契約書は借主側,貸主側双方が署名,押印します。借用書や金銭消費貸借契約書を作成する場合、ポイントは、返す約束をしたこと、借主が金銭を受領済であることの明記です。

お金を貸した後から作成するのが債務承認弁済契約書と呼ばれる書類です。お金を貸すときに書類など作成せずに貸したけど、約束の時期になってもなかなか返してくれないなど、不安があるのであらためて書類を作成したいときに作成します。後から作成しても法的問題はありません。

業務委託契約の解除合意書はお互いが契約解除に合意したことを証明する書面です。法律上必ず作らなければならないというものではありません。また、作らなければ契約を解除できなというものでもありません。後のトラブル防止のため、話し合って合意した内容、特に清算条項を書面にします。

個人的なやり取りにおいて、約束した証拠として又は、事実を確認した証拠として交わされることが多い念書。念書に関して、作成する場面、契約書、合意書、覚書等の書類との違いや法的効力、書き方について。

和解契約書とは和解契約で合意した内容を書面にしたものです。書き方の基本は、「当事者」(誰と誰が),「日付」(いつ),「事実関係」(どんな争いがあって),「和解内容」(話し合いでどのように解決するか)です。和解契約とは、当事者双方が話し合いで互いに譲歩して、その間にある争いを止めることを約束する契約のことをいいます。

仮契約という言葉は広く一般的に使われています。ですが、何故「仮」であるのかを考えて、その効力をはっきりさせる必要があります。たとえタイトルに「仮」と記載されていても、その内容がお互いに何らかの義務を負う内容になっていれば、法的な効力を持つ契約書になります。

利用規約や同意書を作る時に検討する内容や書き方の手順について。WebサービスやWebアプリに限らず、自宅サロンや自宅教室など、ご自身が提供するサービスの利用規約や同意書といった書面を準備していますか?
権利義務書類,ビザ申請在留手続き書類,許認可申請書類などの書類作成

神戸 行政書士オフィス辻下
〒651-1145 兵庫県神戸市北区惣山町4丁目18ー7
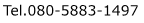 営業時間 10:00〜18:00(土・日・祝祭日 休)
営業時間 10:00〜18:00(土・日・祝祭日 休)
代表 行政書士 辻下仁雄
Profile
大学で応用数学を学び、システムエンジニアとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業し在に至る。
申請取次行政書士 2級ファイナンシャルプランニング技能士