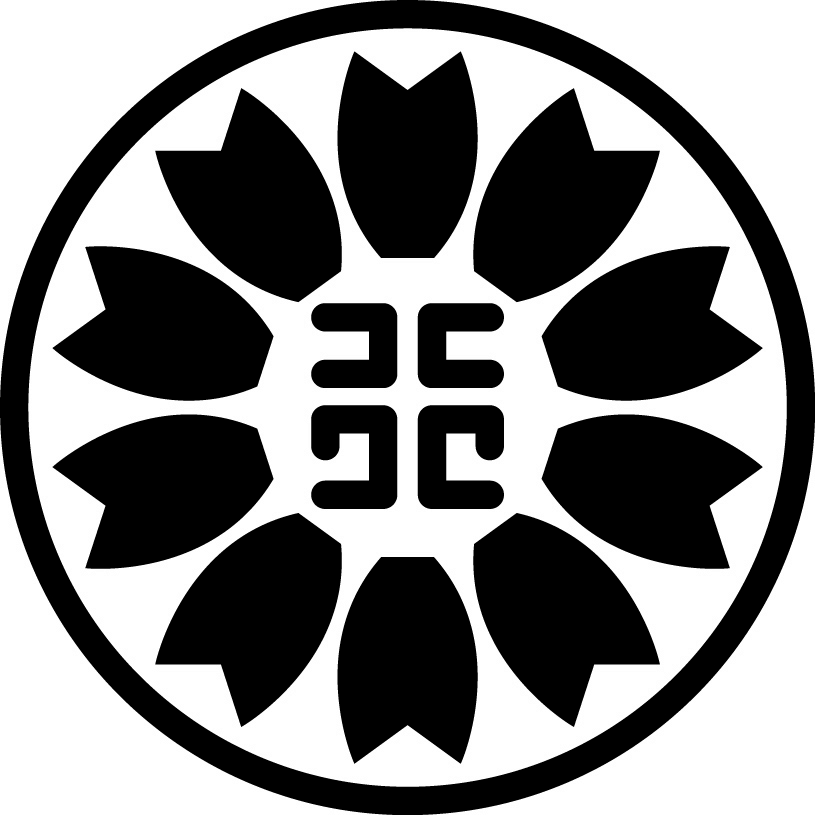権利義務書類,ビザ申請在留手続き書類,許認可申請書類などの関連記事一覧
契約書,合意書,覚書,念書,借用書,和解書,利用規約、ビザ申請,在留手続き、許認可申請手続きなどの書類作成に関する記事の一覧
合意書や念書,覚書など書類の違いや法的効力等、書類一般に関する記事

契約は当事者間に債権債務を発生させます。この債権の履行を相手方に強制できるように明確にしておくことが契約書作成の目的の一つです。契約書を作成する際、内容のチェックポイントは誰が,誰に,何を,何故,いつ,どうさせるのか、が基本です。

仮契約という言葉は広く一般的に使われています。ですが、何故「仮」であるのかを考えて、その効力をはっきりさせる必要があります。たとえタイトルに「仮」と記載されていても、その内容がお互いに何らかの義務を負う内容になっていれば、法的な効力を持つ契約書になります。

無効事由として、契約当事者に関する要件と契約の内容に関する要件が挙げられます。第一に、契約当事者の意思について契約締結時に欠陥がある場合、第二に、法律が効力を認めない場合、第三に、契約の目的が実現不可能の場合などがあります。

契約や合意の当事者は誰か。契約書や合意書など権利義務書類の作成で大切なことは、誰と契約や約束をするのか、つまり当事者は誰かという点です。もし、相手方が存在しないということになれば、契約書を作成した意味が全くないことになってしまいます。

契約書作成時、法律上は署名で十分ですが、記名押印の方が実際的に使われています。合意書,覚書,念書などの他の権利義務書類についても同様ですが、その違いと法律上の意味など、契約書などの書類作成前に知っておきたい基礎知識。

原本,正本,謄本,写しなど契約書関連書類の法律上の差異と効力
皆様はプライベートなやり取りや、日々の暮らしなどで、「この書類は原本?,謄本?、それとも写し?」といったことを意識することはあまり無いと思います。契約書に関しても、私人間の契約で、私人だけで作成した契約書では原本とその写しが考えられるだけです。

皆様は日々の暮らしでの中で契約を意識することはあまりありませんが、色々な契約をしながら暮らしています。しかし、いちいち契約書を作成していません。原則、契約の成立に書面は必要ありません。が、それでも契約書を作成する場面もあります。

契約書や合意書,念書等の権利義務に関する書類の法的効力の有無について。書類の存在や書類のタイトルが法的効力を決めるのではなく、書類内容(法律上の権利や義務の生ずる内容)の事実の有無が法的効力を決めます。

契約書や合意書,念書等の書類のタイトルの違いと法的効力について
契約書、合意書、覚書、念書等のタイトルは作成するケースによって使い分けているだけで、その効力は書かれている内容によって判断します。また、書式も決まった形があるわけではなく自由です。つまり書かれている内容が当事者の関係を規定し、表題は当事者の関係を規定しません。

合意書や覚書は当事者間の合意事項を文書にしたものです。覚書は、一般的に何らかの忘れたくないことや、話し合った内容などを記録として残しておくためのメモとして作成している文書です。合意書、覚書に関する基本事項、その効力や契約書等の他の書類との違いについて。
契約書はじめ、合意書,念書,借用書,和解書など、プライベートで役立つ法律文書関連記事

一旦契約を締結すると、契約の当事者はその内容を守る義務を負います。原則、契約書や合意書等の書類が「有る」とか「無い」とかは関係なく、一方的にやめることはできません。ただ相手方が「そう言うのなら無かったことにしましょう」等と同意してくれる場合は別です。

契約解除の合意書を作成する場合としては、契約を解除することについて当事者双方が納得して合意していることを前提として作成されます。ですが、契約関係を明確にする意味でも、解除する契約の特定と清算条項をポイントとして書面を作成した方が後々のトラブルの防止になります。

合意書や覚書は、基となる契約書に対して付随的・派生的・補足的な内容を記載するイメージがありますが、記載内容によっては契約書と同様に法的効果があります。合意者、覚書を作成するときの基本となる要点と無効とならない法的に有効な書き方について。

個人的なやり取りにおいて、約束した証拠として又は、事実を確認した証拠として交わされることが多い念書。念書に関して、作成する場面、契約書、合意書、覚書等の書類との違いや法的効力、書き方について。

借用書は通常、借主側のみが署名,押印するのに対して、金銭消費貸借契約書は借主側,貸主側双方が署名,押印します。借用書や金銭消費貸借契約書を作成する場合、ポイントは、返す約束をしたこと、借主が金銭を受領済であることの明記です。

お金を貸した後から作成するのが債務承認弁済契約書と呼ばれる書類です。お金を貸すときに書類など作成せずに貸したけど、約束の時期になってもなかなか返してくれないなど、不安があるのであらためて書類を作成したいときに作成します。後から作成しても法的問題はありません。

念書の書き方として決まった書式とかはありません。「いつ何をして、どういう約束だったか」、「それがどうなったか」、「それでどうするのか」といったことを書きます。項目としては、「誰が誰に対して」、「どんな約束」、「いつ実行する」,「場所,方法,手段は」等です。

和解契約書とは和解契約で合意した内容を書面にしたものです。書き方の基本は、「当事者」(誰と誰が),「日付」(いつ),「事実関係」(どんな争いがあって),「和解内容」(話し合いでどのように解決するか)です。和解契約とは、当事者双方が話し合いで互いに譲歩して、その間にある争いを止めることを約束する契約のことをいいます。
ビジネス契約書をはじめ、利用規約や業務委託契約書,秘密保持契約書などの法律文書関連記事

個別契約とは、特定の個々の取引を対象とした契約です。それに対して基本契約とは、一定の継続的取引を対象として各個別取引あるいは個別契約に共通して適用される一般的な基本条件をあらかじめ規定した契約です。

契約書に規定すべき具体的な条項は、個々の契約の類型や目的によってそれぞれ異なります。ですが、おおよそ契約書を作成する際に共通して規定する条項もあります。例えば、契約当事者,契約違反,契約解除等です。これらは「一般条項」と呼ばれます。

業務委託契約の解除合意書はお互いが契約解除に合意したことを証明する書面です。法律上必ず作らなければならないというものではありません。また、作らなければ契約を解除できなというものでもありません。後のトラブル防止のため、話し合って合意した内容、特に清算条項を書面にします。

業務委託契約という契約は民法の契約には存在しません。「一定の仕事を他の者に任せ、その対価として報酬を支払う」という契約内容を、法的性質という観点から見た場合、大きく分けて受託者に仕事の完成を約束させる請負と、受託者に事務処理を約束させる委任に分けられます。

業務委託契約書の作成時、検討しなければならない基本となる条項は、契約目的,委託業務内容,報酬,再委託,損害賠償,解除の6項目が挙げられます。委託する業務内容によって色々考えられますが、本質的な内容は「委託者が一定の業務を委託する」,「委託した業務の対価として受託者に報酬を支払う」の2点です。

利用規約や同意書を作る時に検討する内容や書き方の手順について。WebサービスやWebアプリに限らず、自宅サロンや自宅教室など、ご自身が提供するサービスの利用規約や同意書といった書面を準備していますか?。

システム開発委託契約はシステムの発注者が、受注者に対してシステム開発に関する業務を委託する際に締結する契約のことであり、その時に作成する契約書がシステム開発委託契約書となります。契約の形態は請負か委任、または請負+委任が考えられます。

秘密保持契約書に署名を求められたときに確認する条項のポイント
秘密保持契約書のレビューや作成時のチェックポイントについて。フリーランスや個人事業主が秘密保持契約書への署名を求められた。業務を委託する、あるいは業務提携を検討しているなど秘密保持契約書を作成する必要があるといったときの最低限確認すべきポイントについて。
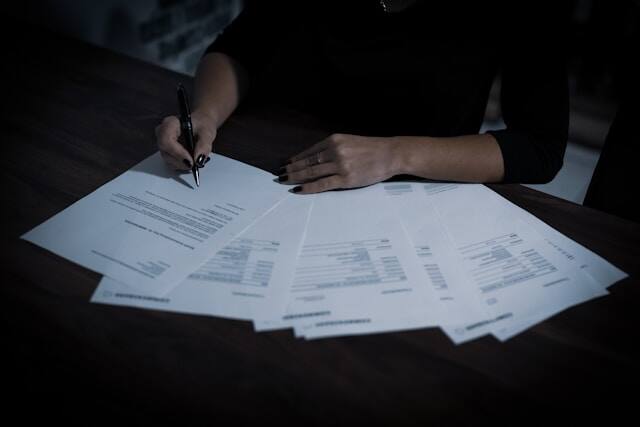
業務委託契約書が読めると、仕事が守れます。仕事がもっと自由になります。フリーランス・個人事業主として、業務委託契約書で読むところは「取り決めた内容が正しく書かれているかどうか」です。具体的には、何の作業をいつまでに完了して、いくらの報酬をいつまでに支払ってくれるのかということです。
ビザ申請,在留手続きに関する記事

外国人が日本で活動するための上陸,在留手続きについて―ビザ(査証)と在留資格―
外国人の在留資格認定証明書による上陸手続。在留資格認定証明書とは、外国人の上陸,在留目的が入管法に定めるいずれかの在留資格に該当しているかどうかを事前に審査を行い、該当していると認められる場合に交付される証明書です。

外国人を雇用する側が押えておく就労ビザ(就労可能な在留資格)の要点
外国人を雇用するには就労可能な在留資格(就労ビザ)のうちのいずれか1つを取得しなければなりません。そして、従事しようとしている業務が、いずれかの在留資格に対応する活動に該当しなければなりません。

在留資格『技術・人文知識・国際業務』の概要 ―ビザ取得のために押さえたい要件―
在留資格「技術・人文知識・国際業務」のビザ申請,取得のために押さえる要件は、「どのような人(外国人)が」、「どのようなところで(企業」など)」、「どのような活動(業務)をするのか」、ということです。

就労ビザの更新許可を申請して引続き日本で働くための手続きについて
就労ビザ(就労可能な在留資格)を持っている外国人は、現に許可されている在留期間の更新を申請し、許可を受けて、引き続き日本で働くことができます。

卒業後、日本の企業に就職した留学生の在留資格変更 ―留学ビザから就労ビザへ―
留学生が卒業後、日本の企業に就職する場合や、企業が留学生を雇用する場合は、入社までに在留資格を、いわゆる就労ビザへ変更する手続きが必要です。変更の手続きは、在留資格変更許可申請書を作成し、変更の許可を受ける必要があります。

在留資格『技能』は、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する外国人が日本で就労するための在留資格です。そのことから、ビザ申請の要件として実務経験が重要視されます。在職証明書等で実務経験を立証することになります。

在留資格『企業内転勤』は海外にある親会社からその日本支店や日本子会社に転勤してくるための就労ビザです。特に押さえるべき要件は「どこ」から「どこ」への転勤か?ということと、転勤元と転勤先企業の関連性及び、その業務内容です。

外国人が、転職で日本での仕事内容が変わり、在留資格を変更したい場合、在留資格変更の許可を申請することができます。ただし、本当に在留資格の変更が必要かどうかは、現に有している在留資格と転職後の仕事内容に関係します。

既に日本に在留している外国人が転職したとき、転職先での業務内容あるいは、転職先の企業自体が、現に有している在留資格(就労ビザ)で許可されるかどうか、就労資格証明書の交付を申請することで事前に確認することができます。

在留資格『留学』や『家族滞在』は日本で報酬を受ける活動(就労)は許可されていませんが、資格外活動許可の制度を利用して、許可を受けて、条件付きですがアルバイトを行うことができます。

資格外活動の許可とは、現に有している在留資格に属さない収入を伴う活動(アルバイトなど)を行おうとする場合に必要となる許可です。資格外活動の許可は包括許可と個別許可の2つの種類があります。
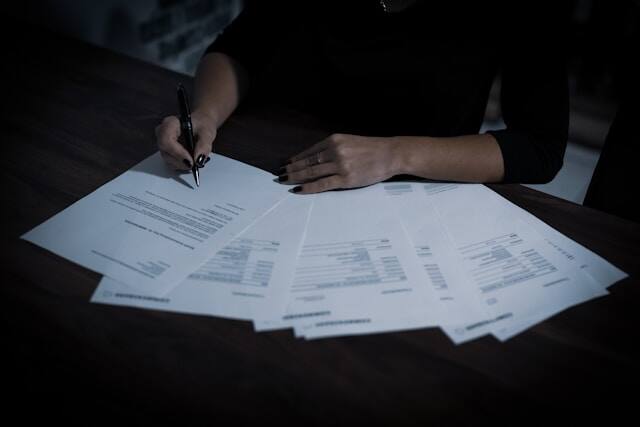
在留資格認定証明書制度を利用した外国人雇用 ―新たに海外から外国人を呼び寄せる―
在留資格認定書証明書の交付を受けた外国人は、これを在外の日本国大使館や総領事館に提示すれば、特段の問題がないかぎり速やかにビザ(査証)が発給されます。
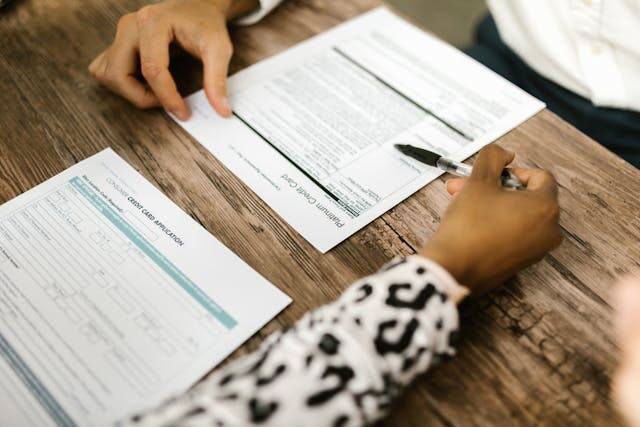
外国人を雇用(採用)する時に知っておきたいビザ申請,在留手続きの流れ
外国人を採用する状況によってビザ申請の手続は異なります。また、就労ビザの取得や更新,変更の申請手続きで不許可になると外国人を雇用できなくなります。ビザ申請は手続の流れを知り、計画的に申請する必要があります。

留学生が卒業後も引続き日本に在留する場合のビザ(在留)手続き
留学生が学校を卒業した場合には、留学ビザは認められないことになり、在留期間が残っていても帰国することが原則です。引続き日本に在留することを希望する場合は、卒業後の日本での活動内容に合った在留資格への変更等が必要です。

外国人留学生が在学中に就職が決まらず、学校卒業後も引続き日本に滞在して就職活動を行いたい場合には、在留資格を『留学』から『特定活動』に変更する手続きが必要です。

就職先が内定し入社まで滞在を希望する留学生のビザ(在留)手続き
就職先は内定しているが学校卒業後あるいは、継続就職活動中に採用が決まった後、入社まで引続き日本に滞在することを希望する留学生の場合、在留資格『特定活動』を取得すれば、入社まで日本に滞在することが可能です。

在留資格『高度専門職』とは、就労可能な在留資格の1つで、「高度学術研究活動」,「高度専門・技術活動」,「高度経営・管理活動」の3つの分野について、高度で専門的な知識や技術を有する外国人(高度外国人材)向けの在留資格です。

在留資格『特定技能』の概要 ―特定技能外国人の雇用を検討するにあたって―
特定技能は特に人手不足の著しい産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるための在留資格です。雇用を検討するにあったて、確認し、準備しておくこと等、特徴的な基準・要件があります。

企業などが特定技能外国人を雇用する場合、自社が法令や省令を遵守し、当該外国人と適切な雇用契約を締結し、当該外国人の日本での職業生活上はもちろん、日常社会生活を含めて支援できる体制を整える必要があります。

特定技能外国人をサポートするために、受け入れ機関には法令で定められた様々な支援が求められます。当該外国人の生活や仕事が円滑に行えるよう、支援計画を作成し、その計画に基づいて支援を行う必要があります。

特定技能外国人を雇用するときに知っておきたいビザ申請手続きの流れ
在留資格『特定技能』の外国人を雇用する(受入れる)には、通常の外国人を雇用する(在留資格を取得する)ためのビザ申請手続きに加えて、『特定技能』特有の手続きが必要になり、事前に確認しておくこと、準備しておくことがいくつかあります。

特定技能ビザ取得のための必要な書類は、就労が可能な他の在留資格と同様に基本的には、申請書類に加えて、在留資格該当性と上陸許可基準省令適合性を満たしていることを立証する書類を提出します。

家族滞在とは、日本で働いている外国人の方や日本に留学中の方の配偶者や子供が日本で一緒に暮らすために取得する在留資格で、就労ビザや留学ビザを有している方の扶養を受けて、日本での日常的な活動を目的とする在留資格です。

家族滞在ビザとは、就労や留学の在留資格を有している外国人の配偶者及び子が扶養を受けて日常的な活動をするための在留資格です。ポイントは呼び寄せる人との家族関係と扶養できる収入や資産を立証することです。

留学生が家族を呼び寄せて一緒に生活したいときは、配偶者と子供に限って、在留資格『家族滞在』(いわゆる家族滞在ビザ)を申請することができます。要件を満たして許可を得れば呼び寄せることができます。

留学生がアルバイトをするには、資格外活動の許可を取得する必要があります。この許可を得れば週に28時間以内という制限がありますが、アルバイトをすることができます。

家族滞在ビザで暮らす外国人がアルバイトをしたい場合のビザ手続き
家族滞在ビザで暮らす外国人がアルバイトをするには、資格外活動の許可を取得する必要があります。この許可を得れば週に28時間以内という制限がありますが、アルバイトをすることができます。

就労資格証明書とは ―転職外国人を雇用(中途採用)するときに知っておきたいこと―
就労資格証明書とは、日本に在留する外国人が行うことができる就労活動を証明する文書で、既に就労可能な在留資格を有してい外国人の在留資格が、新たに就く企業,業務に対して、在留資格の該当性があることの証明です。

在留期間満了後も引続き同じ在留資格をもって在留するすることを希望する場合は、在留期間の更新(いわゆる「ビザの延長」と呼ばれています)を申請し、その許可を受けることが必要です。

在留資格変更(ビザ変更)の許可申請手続き ―在留資格を変更したいとき―
いずれかの在留資格で在留する外国人が、在留中にその目的と活動内容が変わり、別の在留資格をもって在留することが必要となる場合があります。そのような場合に新しい在留資格に変更するために必要な申請手続きが在留資格変更許可申請の手続きです。
お問い合わせ
権利義務書類,ビザ申請書類,許認可申請書類などの作成・手続きについて専門家に聞いてみたいとお考えの方は、お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。
簡易な内容であれば、メール,電話のみで解決する場合もございます。まずは、ご相談,お問い合わせください。ご相談内容によって費用が発生する場合は、別途お見積りいたします。その場での判断・返答は必要ございません。十分ご検討の上、連絡ください。
権利義務書類,ビザ申請在留手続き書類,許認可申請書類などの書類作成

神戸 行政書士オフィス辻下
〒651-1145 兵庫県神戸市北区惣山町4丁目18ー7
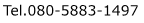 営業時間 10:00〜18:00(土・日・祝祭日 休)
営業時間 10:00〜18:00(土・日・祝祭日 休)
代表 行政書士 辻下仁雄
Profile
大学で応用数学を学び、システムエンジニアとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業し在に至る。
申請取次行政書士 2級ファイナンシャルプランニング技能士