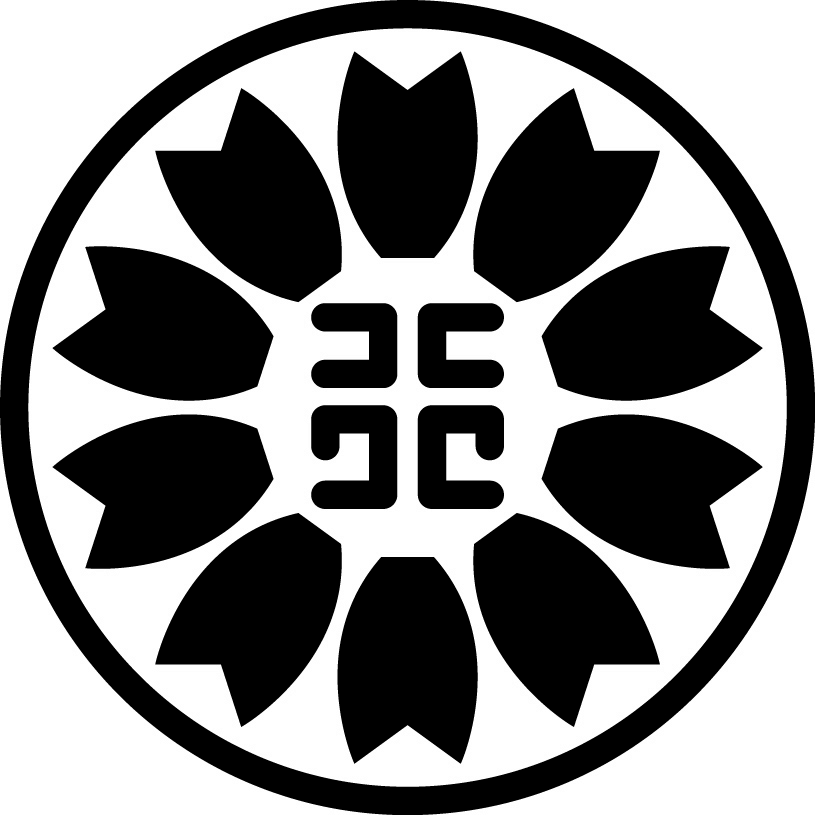日々の暮らしで役立つ法律文書契約書や合意書の作成で大切な契約の当事者について

契約の当事者
契約書の作成で大切なことは、誰と契約をするのか、つまり、契約の当事者は誰かという点です。契約で取り決めた内容の履行を求める相手を確認し、明示することが契約書の作成では最も大切です。
契約書や念書,合意書,借用書などの権利義務書類について、疑問点・不明点等あれば、お問い合わせください。
誰と契約をするのか
何のために契約をするのか、何のために契約書を作成するのか、ということを考えたとき、契約(約束)の相手方に契約の内容を実行してもらう(履行を求める)ために、後日、契約(約束)した証拠として使用できるように作成します。ですが、契約の相手方(履行を求める相手方)が確定していない(誰だかはっきりしない)、あるいは、相手方が存在しないということになれば、契約書を作成した意味が全くないことになってしまいます。また、いかに精緻な契約書を作成しても、契約の主体や効果の帰属先が当事者の意図と異なれば、契約をする意義が失われます。契約書作成で最も大切なことは誰を相手に契約をするのか、つまり、契約の当事者は誰かという点です。当事者の誤りで多いのは、代理人と本人の混同、法人と個人の誤りなどがあります。
確認の方法
契約の相手方の同一性(Aと名乗る者が本当のAであるのか、あるいは、偽っているのか)を確認することは、実際には困難です。友人や知人などよく知っている人との約束を書面にする場合であれば、相手方の同一性の確認は困難でもないですが、初めての相手であれば、個人の場合は印鑑証明と実印の所持者であるということによって、その本人であるということが推測できます。あくまでも推測であって、一応の信用できる材料にすぎません。原則として重要な契約書には、実印を押し、印鑑証明を添付すべきです。より安心するには、住民登録のある住所に、実際に足を運んで当人の存在を確認するか、電話で確かめるなどの手続きをふむことも必要な場面があります。
株式会社や合同会社など法人の場合は、登記簿を閲覧するか、あるいは会社登記簿謄本(登記事項証明書)を取り寄せることによって、本店、資本の額、取締役、監査役の氏名、代表取締役の住所、氏名、共同代表の定めの有無などが確認できます。財団法人、社団法人などの公益法人、宗教法人、医療法人なども登記簿によって調べることができます。
契約当事者をどう表示するか
売買契約の売主と買主、金銭消費貸借契約の貸主と借主、建築請負契約の注文者と請負人、委任契約の委任者と受任者、家屋賃貸借契約の貸主と借主など、いずれも契約の当事者と呼ばれています。
契約当事者とは
契約の当事者とは、法律上の取引当事者であって、契約上の権利義務が帰属し、法律効果が及び、拘束する当事者をさします。契約によって、権利を得、義務を負う当事者です。
契約書での規定例
一般的に、契約書において当事者の正式名称が現れるのは冒頭部分と署名あるいは記名・押印部分の2カ所であり、名称を繰り返すことの煩雑さを避けるとともに閲読の便宜を図るため、各条項においては定義用語(「甲」,「乙」,「売主」,「買主」,「賃貸人」,「賃借人」等)が使用されます。冒頭部分に表れる当事者の記載方法としては、いわゆる前文で契約の主体となる当事者の名称を記載することが一般的です。また、別条項を設けて、当事者の名称のほかに所在地や代表者といった関連事項などを記載する場合もあります。
前文において当事者の名称のみを記載した例
A株式会社(以下、「甲」という。)とB株式会社(以下、「乙」という。)とは、〇〇〇〇につき以下のとおり合意したので、本契約を締結する。
条文を設けて当事者を記載した例
の当事者は、次の各号に揚げるとおりである。
(1)甲:A株式会社
所在地:○○県○○市×××
代表者:〇〇某氏:代表取締役社長
(2)乙:B株式会社
所在地:○○県○○市×××
代表者:〇〇某氏:代表取締役社長
ご相談、お問い合わせ
契約書,合意書,覚書,念書,和解書,借用書など、個人間でも法的書面化が必要とされる場面があります。
行政書士として、客観的視点と法的観点から、冷静に整理・文書化いたします。
関連記事
契約書,合意書など権利義務に関する書類

関連記事
契約内容の基本となるチェックポイント
契約は当事者間に債権債務を発生させます。この債権の履行を相手方に強制できるように明確にしておくことが契約書作成の目的の一つです。契約書を作成する際、内容のチェックポイントは誰が,誰に,何を,何故,いつ,どうさせるのか、が基本です。

関連記事
契約や合意が無効になるとき
無効事由として、契約当事者に関する要件と契約の内容に関する要件が挙げられます。第一に、契約当事者の意思について契約締結時に欠陥がある場合、第二に、法律が効力を認めない場合、第三に、契約の目的が実現不可能の場合などがあります。

関連記事
契約書や合意書,念書など権利義務書類の法的効力
契約書や合意書,念書等の権利義務に関する書類の法的効力の有無について。書類の存在や書類のタイトルが法的効力を決めるのではなく、書類内容(法律上の権利や義務の生ずる内容)の事実の有無が法的効力を決めます。

関連記事
契約書や合意書等の書類を作成する意義とその必要性
皆様は日々の暮らしでので契約を意識することはあまりありませんが、色々な契約をしながら暮らしています。しかし、いちいち契約書を作成していません。原則、契約の成立に書面は必要ありません。が、それでも契約書を作成する場面もあります。
その他、よく読まれている記事

借用書は通常、借主側のみが署名,押印するのに対して、金銭消費貸借契約書は借主側,貸主側双方が署名,押印します。借用書や金銭消費貸借契約書を作成する場合、ポイントは、返す約束をしたこと、借主が金銭を受領済であることの明記です。

お金を貸した後から作成するのが債務承認弁済契約書と呼ばれる書類です。お金を貸すときに書類など作成せずに貸したけど、約束の時期になってもなかなか返してくれないなど、不安があるのであらためて書類を作成したいときに作成します。後から作成しても法的問題はありません。

業務委託契約の解除合意書はお互いが契約解除に合意したことを証明する書面です。法律上必ず作らなければならないというものではありません。また、作らなければ契約を解除できなというものでもありません。後のトラブル防止のため、話し合って合意した内容、特に清算条項を書面にします。

個人的なやり取りにおいて、約束した証拠として又は、事実を確認した証拠として交わされることが多い念書。念書に関して、作成する場面、契約書、合意書、覚書等の書類との違いや法的効力、書き方について。

和解契約書とは和解契約で合意した内容を書面にしたものです。書き方の基本は、「当事者」(誰と誰が),「日付」(いつ),「事実関係」(どんな争いがあって),「和解内容」(話し合いでどのように解決するか)です。和解契約とは、当事者双方が話し合いで互いに譲歩して、その間にある争いを止めることを約束する契約のことをいいます。

仮契約という言葉は広く一般的に使われています。ですが、何故「仮」であるのかを考えて、その効力をはっきりさせる必要があります。たとえタイトルに「仮」と記載されていても、その内容がお互いに何らかの義務を負う内容になっていれば、法的な効力を持つ契約書になります。

利用規約や同意書を作る時に検討する内容や書き方の手順について。WebサービスやWebアプリに限らず、自宅サロンや自宅教室など、ご自身が提供するサービスの利用規約や同意書といった書面を準備していますか?
権利義務書類,ビザ申請在留手続き書類,許認可申請書類などの書類作成

神戸 行政書士オフィス辻下
〒651-1145 兵庫県神戸市北区惣山町4丁目18ー7
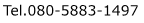 営業時間 10:00〜18:00(土・日・祝祭日 休)
営業時間 10:00〜18:00(土・日・祝祭日 休)
代表 行政書士 辻下仁雄
Profile
大学で応用数学を学び、システムエンジニアとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業し在に至る。
申請取次行政書士 2級ファイナンシャルプランニング技能士