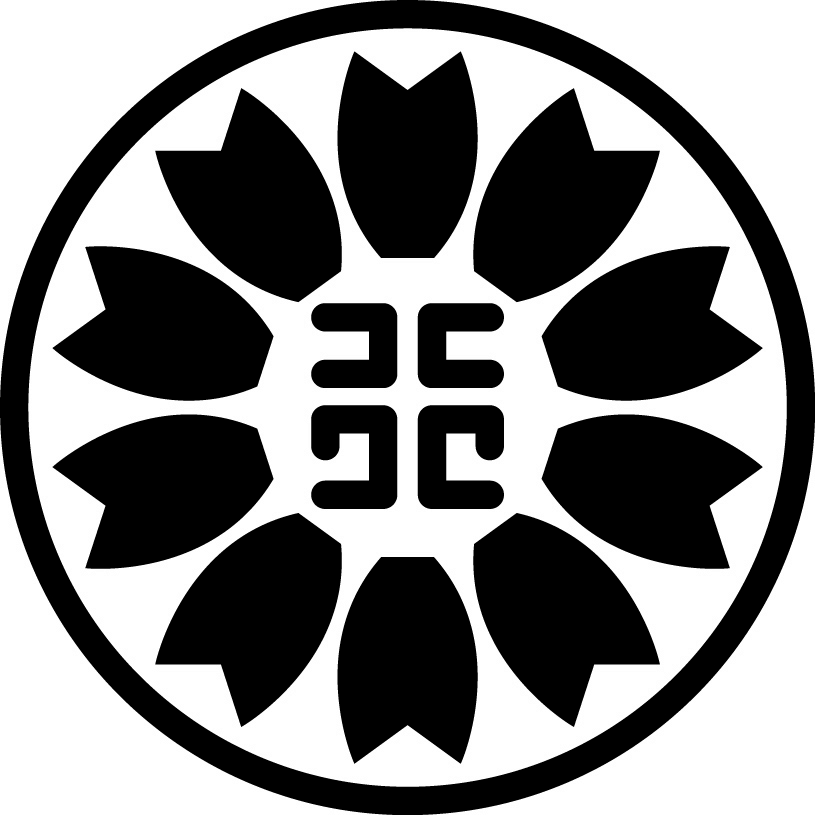日々の暮らしで役立つ法律文書契約書や合意書,念書など権利義務書類の法的効力

法的効力
『法的効力』、この言葉をどのように捉えるかにもよります。例えば、「お金の貸し借りがあって、約束した時期に返済がなかった」という場合、なんとか返済してもらうためには裁判を行うことになりますがそのとき、書類があれば、裁判で「お金を貸した、借りた」という事実があったことを証明するための材料(証拠)にすることができます。裁判上、証拠として有効(役に立つ)という意味では、「法的効力」があるということになります。それは契約書や覚書、念書等を問いません。
契約書や念書,合意書,借用書などの権利義務書類について、疑問点・不明点等あれば、お問い合わせください。
書類に法的効力が「有る」とか「無い」とか
一方、契約書や覚書、念書等があるということが、法律上の権利や義務が発生するための条件(要件)という意味では、「法的効力」はありません。契約書や覚書、念書等の文書があるということが、法律上の権利や義務が発生するための条件(要件)ではありません。ただし例外もあり、書面を必要する場合もあります。「貸したお金を返せ」という請求する権利は契約書や覚書、念書等の文書があるから請求権があるのではなく、そこに書いてあるような事実があるから請求権があるということです。その事実を証明するための有効な手段として文書が存在します。
法的効力の意味
「関係当事者の間で法律によって認められている権利を新たに取得するとか、既に取得している権利を失うとか、新たに義務を負う、負わない」といった法律上の権利義務の取得・喪失・変更を生ずることを「法的効力」と考えます。そうすると、「法的効力」が有るとは、そういった権利義務が生じ、「法的効力」が無いとは、そういった権利義務が生じないということです。「法的効力」の有る無しに文書の存在は関係ありません。法律上の要件を満たせば、権利を取得し義務を負います(文書の存在を必要とする場合もあります)。お金の貸し借りで考えると、返す約束でお金を借りて、実際に金銭を受け取れば、貸した方は法律上認められた「返せという権利」を取得し、借りた方は「返す義務」を負います。つまり法的効力の有る約束をしたということです。また、例えば、友達との帰り際に「また会おうね」という約束をした場合、法律上の権利や義務を生じるとは考えられません。法的効力の無い約束だと思います。
書類の存在
契約書や合意書,覚書、念書等の文書があるだけでは法的効力はありません。契約書や合意書,覚書、念書等の文書は当事者同士の合意事項(約束した内容)を記載した文書として存在しています。合意が本当にあったから記載内容の権利義務を有します。そもそも合意がなければ、いくら文書が存在しても権利や義務が発生することはありません。そこに記載されている内容の合意が本当にあったという事実を証明する証拠として作成されます。証拠としての効力を生ずるためには記載内容に不備があってはいけません。金銭の貸し借りに例えると、「返す約束でお金を借りた」という事実と「実際に金銭の受け渡しがあった」という事実が必要となります。相手方と争うようなことになったとき、文書の内容から「お金を貸します、借ります」という約束をした事実は確認できるけど、「実際にお金の受け渡しがあったかどうか確認できない」というような内容であれば、法的効力を生じない、つまり「返せという権利が生じない」という可能性がでてきます。そうすると、その文書(契約書でも、合意書、念書でもかまいません)には法的効力が無いと考えることもできます。また、記載内容に嘘はないけど、その内容が不法行為だとか公序良俗に反するような内容であれば、当然、法律によって認められていることはないので、権利や義務は生じません。ただ、繰り返しになりますが、文書の存在やその文書のタイトルが法的効力の有無を決めるのではなく、その文書に書いてある内容(法律によって認められている権利や義務の生ずる内容)の事実が本当にあったのか無かったのかが法的効力の有無を決めます。
書類の法的効力
「お金を返してもらう約束で貸した。実際に金銭を渡した」という内容の「約束(契約)」に法的効力があるかといえば、その「約束(契約)」には法的効力があります。その約束の内容を記載した「文書」(契約書でも合意書でも念書でもかまいません)に法的効力があるかといえば、法的効力があることを証明するのに有効です、ということです。
法的拘束力について
ここでは契約(約束)における法的拘束力について考えます。法的拘束力があるとは、その約束を守る義務があるということで、相手方が守らなかった(義務を果たさなかった)場合には、国(裁判所)の協力を得て、その結果を実現してくれることと考えます。国(裁判所)の協力を得るには、その結果を求める権利がある(つまり、約束した内容に法的効力がある)ことが前提で、その権利を認めてもらう有効な証拠として文書(契約書、合意書、覚書や念書)を作成するということです。「お金を返す約束で貸した」という事実があれば、返還を請求する権利があるということです。相手方が素直に返してくれれば、何も問題ありません、それまでです。ただ、相手方が返してくれなかったとき、裁判所が協力して貸した事実があったかどうか判断します。事実が認められれば、返せという権利が認められ、返せと命令してくれますし、強制もしてくれます。事実が無いと定まれば、返還を請求する権利が無いことになります。このことは、「貸したにもかかわらず、返還請求権がない」ということではなく、「貸した事実がないことになってしまった(貸した事実が認められなかった)から返還を請求する権利もない」ということです。
「法的拘束力」が有るとか、無いとかは取得した権利を実現するためや、負った義務を果たしてもらうために国(裁判所)の協力を得ることができるかどうかということです。
当オフィスでは個人のお客様向けとして、合意書や念書,覚書,借用書,和解書,契約解除など、書類の作成サービスをリーズナブルな価格設定で提供しています。法的に整った書面をあなたの言葉から専門家が作成します。書き方の不安は不要です。
ご相談,お問い合わせ
契約書,合意書,覚書,念書,和解書,借用書など、個人間でも法的書面化が必要とされる場面があります。
行政書士として、客観的視点と法的観点から、冷静に整理・文書化いたします。
法的効力を備えた書面で、曖昧な約束を明確に。個人間トラブルを未然に防ぐ専門支援。
ご事情の整理から文案作成まで、丁寧に伴走します。
関連記事
契約書,合意書など権利義務に関する書類

関連記事
契約書や合意書などの書類作成の意義とその必要性
皆様は日々の暮らしでの中で契約を意識することはあまりありませんが、色々な契約をしながら暮らしています。しかし、いちいち契約書を作成していません。原則、契約の成立に書面は必要ありません。が、それでも契約書を作成する場面もあります。

関連記事
合意書や覚書の効力と契約書との違い
合意書や覚書は当事者間の合意事項を文書にしたものです。覚書は、一般的に何らかの忘れたくないことや、話し合った内容などを記録として残しておくためのメモとして作成している文書です。合意書、覚書に関する基本事項、その効力や契約書等の他の書類との違いについて

関連記事
仮契約の法的効力
仮契約という言葉は広く一般的に使われています。ですが、何故「仮」であるのかを考えて、その効力をはっきりさせる必要があります。たとえタイトルに「仮」と記載されていても、その内容がお互いに何らかの義務を負う内容になっていれば、法的な効力を持つ契約書になります。

関連記事
契約書や合意書,念書等の書類のタイトルの違いと法的効力について
契約書、合意書、覚書、念書等のタイトルは作成するケースによって使い分けているだけで、その効力は書かれている内容によって判断します。また、書式も決まった形があるわけではなく自由です。つまり書かれている内容が当事者の関係を規定し、表題は当事者の関係を規定しません。
その他、よく読まれている記事

借用書は通常、借主側のみが署名,押印するのに対して、金銭消費貸借契約書は借主側,貸主側双方が署名,押印します。借用書や金銭消費貸借契約書を作成する場合、ポイントは、返す約束をしたこと、借主が金銭を受領済であることの明記です。

お金を貸した後から作成するのが債務承認弁済契約書と呼ばれる書類です。お金を貸すときに書類など作成せずに貸したけど、約束の時期になってもなかなか返してくれないなど、不安があるのであらためて書類を作成したいときに作成します。後から作成しても法的問題はありません。

業務委託契約の解除合意書はお互いが契約解除に合意したことを証明する書面です。法律上必ず作らなければならないというものではありません。また、作らなければ契約を解除できなというものでもありません。後のトラブル防止のため、話し合って合意した内容、特に清算条項を書面にします。

個人的なやり取りにおいて、約束した証拠として又は、事実を確認した証拠として交わされることが多い念書。念書に関して、作成する場面、契約書、合意書、覚書等の書類との違いや法的効力、書き方について。

和解契約書とは和解契約で合意した内容を書面にしたものです。書き方の基本は、「当事者」(誰と誰が),「日付」(いつ),「事実関係」(どんな争いがあって),「和解内容」(話し合いでどのように解決するか)です。和解契約とは、当事者双方が話し合いで互いに譲歩して、その間にある争いを止めることを約束する契約のことをいいます。

仮契約という言葉は広く一般的に使われています。ですが、何故「仮」であるのかを考えて、その効力をはっきりさせる必要があります。たとえタイトルに「仮」と記載されていても、その内容がお互いに何らかの義務を負う内容になっていれば、法的な効力を持つ契約書になります。

利用規約や同意書を作る時に検討する内容や書き方の手順について。WebサービスやWebアプリに限らず、自宅サロンや自宅教室など、ご自身が提供するサービスの利用規約や同意書といった書面を準備していますか?
権利義務書類,ビザ申請在留手続き書類,許認可申請書類などの書類作成

神戸 行政書士オフィス辻下
〒651-1145 兵庫県神戸市北区惣山町4丁目18ー7
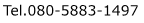 営業時間 10:00〜18:00(土・日・祝祭日 休)
営業時間 10:00〜18:00(土・日・祝祭日 休)
代表 行政書士 辻下仁雄
Profile
大学で応用数学を学び、システムエンジニアとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業し在に至る。
申請取次行政書士 2級ファイナンシャルプランニング技能士