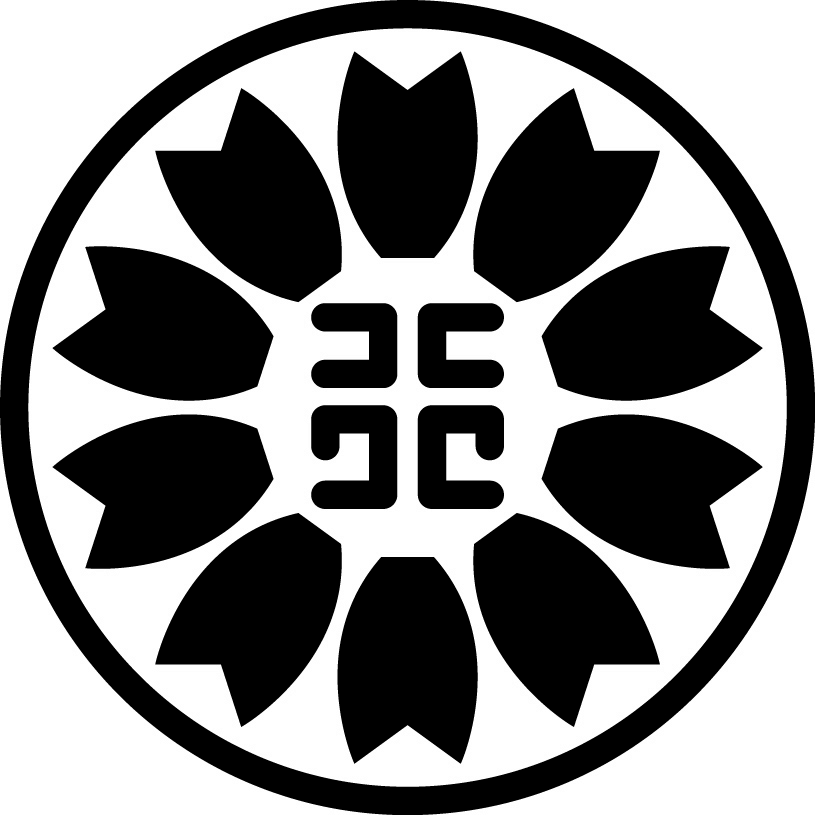日々の暮らしで役立つ法律文書契約書や合意書などの書類を作成する意義とその必要性
書類作成の意義
皆様はプライベートなやり取りや日々の暮らしなどで契約を意識することはあまりありませんが、日々、色々な契約をしながら暮らしています。例えば、キップを買って電車に乗ることや、スーパーでの買い物なども契約です。しかし、契約書という書類を作成し、署名してお互いに交わすことはほとんどしていません。原則、契約を結ぶのに書類は必要ありません。
契約書や念書,合意書,借用書などの権利義務書類について、疑問点・不明点等あれば、お問い合わせください。
書類を作成する意義とその必要性
契約と契約書
原則、書類を必要としない契約でも、契約書を作成するのは何故でしょう。そもそも契約とは、言ってみれば「約束」です。それも単なる約束ではなく「お互いの権利・義務に関する約束」をいいます。例えば、友達との帰り際に「また会おうね」というのは約束だと思いますが、契約ではないと思います。個人間の約束でも、いざとなれば裁判所などの国の力を借りてでも強制的に守らせることができような明確な約束です。もう少し堅い言葉でいうと、「相対立する二つ以上の意思表示の合致によって成立する法律行為」のことを言います。「当事者の一人がある効果を望んで、その効果を望む旨の意思を相手方に示して、相手方がその意思に対して応じる意思を示し、お互いの意思表示が合致することで成立し、法律上の効果が生じる」ことをいいます。例えば甲さんがケーキ屋さんでショートケーキを食べたいと思い、ショートケーキを自分の物にすることを望んで、「このショートケーキを下さい」と意思を示し、店員さんが「○○円頂きます」とその意思に応じる意思を示し、甲さんと店員さんの意思が合致し契約(売買契約)が成立します。契約が成立したので、法律上の効果として、甲さんは店員に対して「ショートケーキを引き渡してください」という権利が生じ、同時に代金○○円を支払う義務が生じます。店員には甲さんに対して「代金○○円支払って下さい」という権利が生じ、同時にショートケーキを引き渡す義務が生じます。先ほどの「また会おうね」では、いつ会うのか、どこで会うのかなど明確ではありません。約束だと思いますが、裁判所に行って強制的に守らせる事柄とも思えません。おそらく契約ではないと思います。一方、契約書は契約の内容(約束した内容)を詳細に書面にしたものです。約束の当事者は誰か、いつ約束したか、いつからその約束の効力があるか、どんな権利と義務があって、どんな場合に権利が発生し、義務が発生するのか、その権利は誰のもので、その義務はだれが負うのか、対象としている物は何で、その数量・値段はいくらか、約束を守れなかった場合はどうするのか、突発的な非常事態で約束がを守れなかった場合はどうするのか、その場合誰がリスクを負うのか、どんな場合に約束したことを無かったことにするのか、約束を無かったことにした場合お互いどうするのか、トラブルが発生した時はお互いどうするのか等々、個別具体的な内容が詳細に書かれています。先ほどのケーキの買い物でも、意識していなくても法律上の権利・義務は発生してます。が、法律書を持ち出してわざわざ調べながら契約書を作成し、ケーキを買わないと思います。書面にする必要がない場合と書面を作成する必要がある場合を考えることが必要です
契約書や合意書などの書類作成の意義とその必要性
契約は契約書のことではありません。契約の成立に契約書の作成は必要ではなく、口頭でも契約は成立します。では何故、契約「書」を作成するのでしょうか。一様ではありませんが、契約当事者間における行為規範の明確化とトラブル発生時の行為規範の明確化があると思います。言葉を変えて言うと、書面を残しておけば、契約の締結後、各当事者は契約内容の実現に向けて何をすべきか、契約内容の実現後、各当事者は何をすべきかといった事柄が明確になります。誰とどんな内容の約束をしたのかが証拠として残ります。後日、記憶が曖昧になったり又は、相手が約束した内容と異なる主張をしても、書面を残しておけば、一目瞭然です。後々のトラブルを未然に防止できます。書面にした内容を読み返すことによって、お互いの意識のズレや内容の見落としを減らすことができます。後々、「こんなはずではなかった」あるいは、「そういうつもりではなかった」という状況を減らすことができます。又、内容の不履行が生じたり、当事者間で意見の食い違いが生じたとき、仲裁や裁判所等の紛争解決機関の判断の拠りどころすべき規範が明確になります。そのためには内容・表現が明確であること。複数の人が読んでも一つの意味にしか受けとらない内容であることです。約束・取決めをした当事者を明確にしておくことです。内容が明確であっても誰と誰の約束か又は、誰からの申し入れかが曖昧であれば意味がありません。後々のトラブルの原因となります。契約書は堅苦しいと思うかもしれませんが、覚書でも何でも変わりはありません。書面に残すことが大切です。
―行政書士による”予防法務”―
日々の暮らしで役立つ法律文書作成のサポート
契約書,合意書,覚書,念書,和解書,借用書など、個人間でも法的書面化が必要とされる場面があります。「裁判までは考えていないけれど、口約束のままだと不安」、「後々もめたくない」、そんな時に役立つのが 行政書士による予防法務サービス です。暮らしの中の小さな取り決めを、安心の書面にして、未来のトラブルを防ぎます。行政書士として、客観的視点と法的観点から、冷静に整理・文書化いたします。当オフィスでは、合意書や念書,覚書,借用書,和解書,契約解除など、書類の作成サービスをリーズナブルな価格設定で提供しています。法的に整った書面をあなたの言葉から専門家が作成します。書き方の不安は不要です。
ご相談,お問い合わせ
法的効力を備えた書面で、曖昧な約束を明確に。個人間トラブルを未然に防ぐ専門支援。
ご事情の整理から文案作成まで、丁寧に伴走します。
関連記事
契約書,合意書など権利義務に関する書類

関連記事
契約書や合意書,念書等の権利義務に関する書類の法的効力の有無について。書類の存在や書類のタイトルが法的効力を決めるのではなく、書類内容(法律上の権利や義務の生ずる内容)の事実の有無が法的効力を決めます。

関連記事
合意書や覚書は当事者間の合意事項を文書にしたものです。覚書は、一般的に何らかの忘れたくないことや、話し合った内容などを記録として残しておくためのメモとして作成している文書です。合意書、覚書に関する基本事項、その効力や契約書等の他の書類との違いについて

関連記事
仮契約という言葉は広く一般的に使われています。ですが、何故「仮」であるのかを考えて、その効力をはっきりさせる必要があります。たとえタイトルに「仮」と記載されていても、その内容がお互いに何らかの義務を負う内容になっていれば、法的な効力を持つ契約書になります。

関連記事
契約は当事者間に債権債務を発生させます。この債権の履行を相手方に強制できるように明確にしておくことが契約書作成の目的の一つです。契約書を作成する際、内容のチェックポイントは誰が,誰に,何を,何故,いつ,どうさせるのか、が基本です。
その他、よく読まれている記事

借用書は通常、借主側のみが署名,押印するのに対して、金銭消費貸借契約書は借主側,貸主側双方が署名,押印します。借用書や金銭消費貸借契約書を作成する場合、ポイントは、返す約束をしたこと、借主が金銭を受領済であることの明記です。

お金を貸した後から作成するのが債務承認弁済契約書と呼ばれる書類です。お金を貸すときに書類など作成せずに貸したけど、約束の時期になってもなかなか返してくれないなど、不安があるのであらためて書類を作成したいときに作成します。後から作成しても法的問題はありません。

業務委託契約の解除合意書はお互いが契約解除に合意したことを証明する書面です。法律上必ず作らなければならないというものではありません。また、作らなければ契約を解除できなというものでもありません。後のトラブル防止のため、話し合って合意した内容、特に清算条項を書面にします。

個人的なやり取りにおいて、約束した証拠として又は、事実を確認した証拠として交わされることが多い念書。念書に関して、作成する場面、契約書、合意書、覚書等の書類との違いや法的効力、書き方について。

和解契約書とは和解契約で合意した内容を書面にしたものです。書き方の基本は、「当事者」(誰と誰が),「日付」(いつ),「事実関係」(どんな争いがあって),「和解内容」(話し合いでどのように解決するか)です。和解契約とは、当事者双方が話し合いで互いに譲歩して、その間にある争いを止めることを約束する契約のことをいいます。

仮契約という言葉は広く一般的に使われています。ですが、何故「仮」であるのかを考えて、その効力をはっきりさせる必要があります。たとえタイトルに「仮」と記載されていても、その内容がお互いに何らかの義務を負う内容になっていれば、法的な効力を持つ契約書になります。

利用規約や同意書を作る時に検討する内容や書き方の手順について。WebサービスやWebアプリに限らず、自宅サロンや自宅教室など、ご自身が提供するサービスの利用規約や同意書といった書面を準備していますか?
権利義務書類,ビザ申請在留手続き書類,許認可申請書類などの書類作成

神戸 行政書士オフィス辻下
〒651-1145 兵庫県神戸市北区惣山町4丁目18ー7
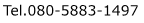 営業時間 10:00〜18:00(土・日・祝祭日 休)
営業時間 10:00〜18:00(土・日・祝祭日 休)
代表 行政書士 辻下仁雄
Profile
大学で応用数学を学び、システムエンジニアとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業し在に至る。
申請取次行政書士 2級ファイナンシャルプランニング技能士