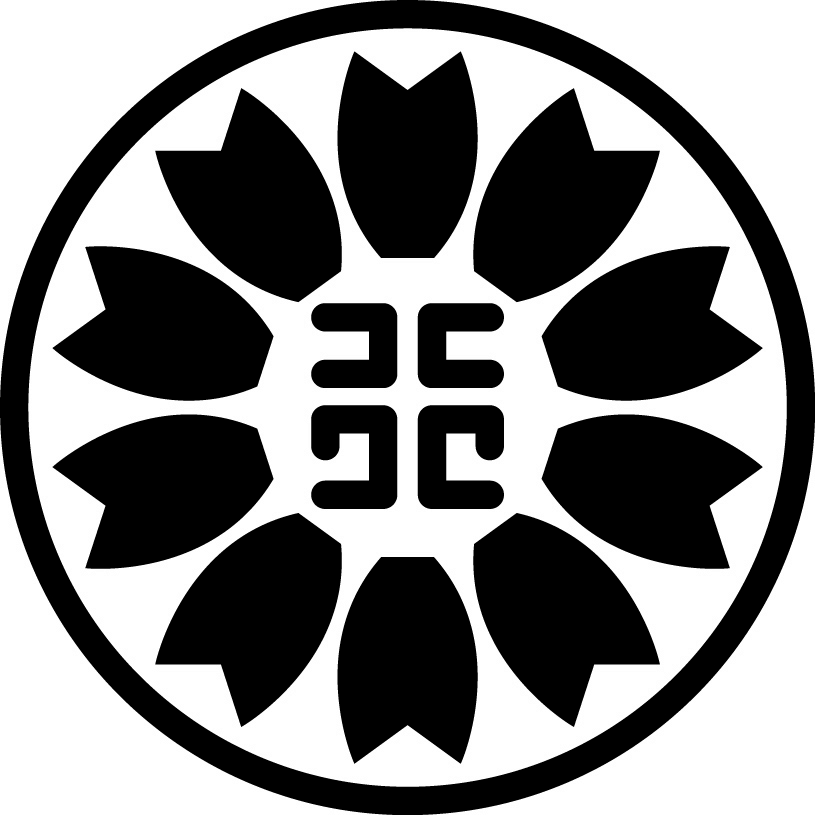ビジネス契約書などの法律文書の作成利用規約や同意書の書き方と作成するときのポイント
ビジネス契約書などの法律文書作成 / 利用規約や同意書の書き方と作成するときのポイント
ビジネス契約書などの法律文書の作成
WebサービスやWebアプリ,Webサイトなどインターネットを利用したサービスに限らず、個人事業主やフリーランサー,自宅サロン,自宅教室を検討の方など、ご自身が提供するサービスに関して、同意書や利用規約を用意していますか?。
利用規約や同意書についての書類作成など、お困りごと等あれば、まずは無料のご相談をご利用ください。
当オフィスでは、自宅サロンを運営されている個人向けに『利用規約・同意書セット作成の専用サービス』を提供しております。サービスの詳細はこちらを参照ください。
同意書や利用規約とはどういった書面か
同意書や利用規約は法律上必ず作らなければならいというものではありません。サービスの提供者と利用者との間でのトラブルを未然に防ぎ、万が一、トラブルが発生した場合、書面があれば、まず書面に従って解決が図られます。トラブルが発生したときには、解決へ向けての起点になる書面です。
利用規約
サービスの提供者が提供するサービスを利用者が利用する際、利用するための条件,規則,約束事など、そのサービスの利用者が守らなければならないルールなどを定めたものです。法律的にはサービス提供者と利用者の間の民法上の契約になり、利用規約の内容が契約の内容になります。ただ、書面を準備すれば良いというわけではなく、利用者は提示された利用規約に同意することで、ルールに従う義務が生じます。サービスを利用するためには同意が必要になるということです。「このようなルールでサービスを提供すます、あるいは、このようなルールに従ってもらえればサービスを利用できます、よろしいですね」ということです。
同意書
相手の意見に対して「同意します」という意思表示を書面にしたものです。利用規約や同意書に記載されている内容について有効な同意があったことを証明する証拠として機能します。主にサービスの利用者に発生した損害について、サービス提供者の損害賠償責任を制限,免除するためのルールを記載した、いわゆる「免責事項」に利用されます。ただ、証拠となるには、書面に署名があるだけではなく、利用者が読んで内容を理解し、利用者の自由な意思に基づいて同意していることが必要です。
利用規約がサービス利用上のルールを定めたものに対して、同意書は証拠の意味合いがあり、ルールに従うことに同意したという事実を証明する書面になります。利用規約が同意書を兼ねている場合や、利用規約の一項目として同意項目を記載している場合もあります。また、利用規約とは別に同意書を作成する場合もあります。ご自身が提供を考えてるサービスに合わせて検討する必要があります。
利用規約や同意書の書き方と作成するときのポイント
同意書や利用規約を作成する場合、重要なことは、もちろん提供を考えてるサービスの内容を十分に検討することです。提供するサービスの内容によって独自の用語がある場合は、用語の定義を検討します。以下、基本となるポイントは
- 提供するサービスの内容,用語の定義
- 提供するサービスを利用するうえで利用者に守ってほしいこと、逆にやってほしくないこと
- ルールを守らなかった場合、どんな対処が考えられるか
- ご自身(サービスの提供者)で責任が持てること、持てないこと
などです
同意を得る
利用規約や同意書の書面を用意しても利用者からの同意を得ていなければ、意味がありません。書面の内容が契約内容になることを明記のうえ、同意を得てはじめて書面の内容が契約内容となります。同意書として書面を用意する場合、決まったフォームはありません。基本は「同意する内容」と「同意する旨」を書面に書いてあることです。「同意する内容」としては、先に検討した「1.提供するサービスの内容」や「2.提供するサービスを利用する上で守って欲しいルール」など、始めに検討した内容になります。重要なことは、「署名」と「署名した日付」です。日付と署名があって初めて、同意があったとういう「事実」を証明できます。あとはタイトルですが、タイトルはさほど重要ではありません。何でもいいですが、誤解を招かないように「何に対する同意か」が分かるようなタイトルを付けます。「同意する旨」については、単に署名があるだけでなく、内容を理解していることが重要です。
例えば、署名欄には以下のような記載が考えられます。
私(利用者)は、本同意書記載事項の説明を受け、内容を確認し、十分理解したうえで同意した証として以下に署名します。
署名日付○○○○年○○月○○日
名前
住所
などです。
又、書面の前文として以下のような内容を記載し
本書(利用規約又は同意書)はサービスの提供条件及び利用者との間の権利関係を定めています。サービスの利用に際しては、本書の全文をお読みいただき、内容を理解のうえで、本書に同意して頂く必要があります。
書面の内容が契約内容になることを明記し、利用に際しては同意をして頂く必要があることを明記します。
同意する内容(提供するサービスを利用するうえで守ってほしいルールや禁止事項など)
サービスを利用する上で守ってほしいルールや、逆にやってほしくないこと(禁止事項)をわかりやすく明記します。場合によってはチェックボックスを設けて箇条書きで明記し、利用者にチェックマークを入れてもらいます。
例えば、以下のような記載が考えられます。
利用者は本サービスを利用するにあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為又は該当するとサービス提供者(当社,当オフィスなど)が判断する行為を禁止します。
□ 1.法令に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為
□ 2.公序良俗に反する行為
など一般的な事項のほか、サービス特有のルールや禁止事項をできるだけ具体的に列挙します。
ただ、最初から全ての禁止事項を列挙することは現実的には困難です。禁止事項のどれにも明確に該当しないケースが出てくる可能性もあります。そのような場合の対策として以下のような、いわゆる包括条項(バスケット条項)を明記しておくことも検討します。
□ その他、サービス提供者(当社,当オフィスなど)が不適切と判断する行為
免責事項に関する内容(サービス利用の中断,停止やサービス利用時,利用後のリスクや損害賠償など)
天災や風水害,火災など不可抗力によってサービスの中断や停止などをしなければならない場合があります。また、利用者の禁止行為違反によりサービスの提供や利用を停止する場合もあります。あるいはサービス利用時や利用後のリスクなどがあれば、どのようなリスクが考えられるかを十分に検討し、明記してこくことが重要です。その結果、利用者に損害が発生する可能性もあり得ます。そのような場合、サービスの提供者側でどの範囲まで責任を負い、どの範囲では免責されるのかを明確に定めておくことが重要です。以下のような条項が考えられます。
本書の規定に基づき行った措置により利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。
あるいは、
何らかの理由により責任を負う場合であっても、利用者が支払ったサービス利用の対価の金額を超えて賠償する責任を負わないものとします。
例外的に責任を負う場合であっても、その上限を明確に規定します。ただ、このような規定は消費者契約法という法律により無効となる場合があります。そのため
当社(当オフィスなど)は、故意又は重過失による場合を除き〜
など、故意,重過失によって発生した損害を免責の対象から除外する条項を規定することも検討します。その他、「利用規約や同意書の条項の一部が無効と判断された場合でも、書面そのものや、その他の条項まで無効とはならない」ということを明記することも検討します。
いずれも提供するサービス内容とそのリスクを十分に検討して書面を作成していくことが必要です。
個人情報(利用者情報)の取扱
サービス提供者が利用者から得る情報としては、個人情報を含む利用者情報があります。一般的に利用者情報の取扱はプライバシーポリシーを別途定めますが、プライバシーポリシーについても、利用規約や同意書の一部として利用者の同意を得るため以下のような記載が考えられます。
サービス提供者による利用者情報の取扱については、別途プライバシーポリシーの定めによるものとします。利用者はこのプライバシーポリシーに従ってサービス提供者が利用者情報を取り扱うことに同意するものとします。
などは、ひな型を利用して作成できますが、どういった情報が個人情報に該当するかは提供するサービスによって異なってきます。第三者提供,開示,訂正及び停止等もある程度ひな型を利用できますが、収集方法や利用方法は提供するサービスによって異なるため十分に検討する必要があります。
その他
その他には、裁判管轄や準拠法,規約の変更などが考えられますが、インターネットなどのひな型を利用して、ある程度作ることが可能です。サービス特有というわけではなく共通した項目と考えられます。書面の中心となるのは、「提供するサービス内容」,「禁止事項」,「リスクと免責事項」,「サービスの中断と停止」,「同意を得る」ことです。わかり易い書面を心掛けても堅苦しい文言になりがちです。利用者が読みやすい書面を考えた場合、利用規約や同意書の説明用の要約版を作成することも検討できます。
契約書や合意書,念書などの書類について専門家に聞いてみたいとお考えの方は、お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。
フリーランスや個人事業主様、書類作成で困り事はありませんか?

専門家への相談が近道です。
一人ひとりに合わせたオーダーメイド対応。画一的なテンプレートではなく、ご依頼者様の目的達成のため、情報を的確に整理し個別最適化された書類をご提案,作成致します。
「こんなこと聞いていいのかな・・・」と思ったら、聞いてください。初回ご相談は無料となっています、お気軽にご相談,お問い合わせください。事前にご連絡を頂ければ営業時間外でも対応いたします。
行政書士オフィス辻下
簡易な内容であれば、メール,電話のみで解決する場合もございます。まずは、ご相談,お問い合わせください。ご相談内容によって費用が発生する場合は、別途お見積りいたします。その場での判断・返答は必要ございません。十分ご検討の上、連絡ください。
営業時間 10:00〜18:00(土・日・祝祭日 休)
サービスのご案内
個人サロン向け専用サービス
トラブルは”起きてから”では遅いものです。トラブルが起きる前に利用規約や同意書などの書面を準備していますか?。
個人サロン運営に必要な利用規約や同意書を神戸の行政書士が作成します。「まずは無料相談」から始める予防法務で、安心のサロン運営体制を築けます。
ビジネス契約書などの法律文書関連記事
![]()
前の記事
業務委託契約の解除合意書の条項例
業務委託契約の解除合意書はお互いが契約解除に合意したことを証明する書面です。法律上必ず作らなければならないというものではありません。また、作らなければ契約を解除できなというものでもありません。後のトラブル防止のため、話し合って合意した内容、特に清算条項を書面にします。
![]()
次の記事
秘密保持契約書に署名を求められたときに確認する条項のポイント
秘密保持契約書のレビューや作成時のチェックポイントについて。フリーランスや個人事業主が秘密保持契約書への署名を求められた。業務を委託する、あるいは業務提携を検討しているなど秘密保持契約書を作成する必要があるといったときの最低限確認すべきポイントについて。
その他、よく読まれている記事
![]()
借用書は通常、借主側のみが署名,押印するのに対して、金銭消費貸借契約書は借主側,貸主側双方が署名,押印します。借用書や金銭消費貸借契約書を作成する場合、ポイントは、返す約束をしたこと、借主が金銭を受領済であることの明記です。
![]()
お金を貸した後から作成するのが債務承認弁済契約書と呼ばれる書類です。お金を貸すときに書類など作成せずに貸したけど、約束の時期になってもなかなか返してくれないなど、不安があるのであらためて書類を作成したいときに作成します。後から作成しても法的問題はありません。
![]()
業務委託契約の解除合意書はお互いが契約解除に合意したことを証明する書面です。法律上必ず作らなければならないというものではありません。また、作らなければ契約を解除できなというものでもありません。後のトラブル防止のため、話し合って合意した内容、特に清算条項を書面にします。
![]()
個人的なやり取りにおいて、約束した証拠として又は、事実を確認した証拠として交わされることが多い念書。念書に関して、作成する場面、契約書、合意書、覚書等の書類との違いや法的効力、書き方について。
![]()
和解契約書とは和解契約で合意した内容を書面にしたものです。書き方の基本は、「当事者」(誰と誰が),「日付」(いつ),「事実関係」(どんな争いがあって),「和解内容」(話し合いでどのように解決するか)です。和解契約とは、当事者双方が話し合いで互いに譲歩して、その間にある争いを止めることを約束する契約のことをいいます。
![]()
仮契約という言葉は広く一般的に使われています。ですが、何故「仮」であるのかを考えて、その効力をはっきりさせる必要があります。たとえタイトルに「仮」と記載されていても、その内容がお互いに何らかの義務を負う内容になっていれば、法的な効力を持つ契約書になります。
![]()
利用規約や同意書を作る時に検討する内容や書き方の手順について。WebサービスやWebアプリに限らず、自宅サロンや自宅教室など、ご自身が提供するサービスの利用規約や同意書といった書面を準備していますか?

前の記事
業務委託契約の解除合意書の条項例
業務委託契約の解除合意書はお互いが契約解除に合意したことを証明する書面です。法律上必ず作らなければならないというものではありません。また、作らなければ契約を解除できなというものでもありません。後のトラブル防止のため、話し合って合意した内容、特に清算条項を書面にします。

次の記事
秘密保持契約書に署名を求められたときに確認する条項のポイント
秘密保持契約書のレビューや作成時のチェックポイントについて。フリーランスや個人事業主が秘密保持契約書への署名を求められた。業務を委託する、あるいは業務提携を検討しているなど秘密保持契約書を作成する必要があるといったときの最低限確認すべきポイントについて。

借用書は通常、借主側のみが署名,押印するのに対して、金銭消費貸借契約書は借主側,貸主側双方が署名,押印します。借用書や金銭消費貸借契約書を作成する場合、ポイントは、返す約束をしたこと、借主が金銭を受領済であることの明記です。

お金を貸した後から作成するのが債務承認弁済契約書と呼ばれる書類です。お金を貸すときに書類など作成せずに貸したけど、約束の時期になってもなかなか返してくれないなど、不安があるのであらためて書類を作成したいときに作成します。後から作成しても法的問題はありません。

業務委託契約の解除合意書はお互いが契約解除に合意したことを証明する書面です。法律上必ず作らなければならないというものではありません。また、作らなければ契約を解除できなというものでもありません。後のトラブル防止のため、話し合って合意した内容、特に清算条項を書面にします。

個人的なやり取りにおいて、約束した証拠として又は、事実を確認した証拠として交わされることが多い念書。念書に関して、作成する場面、契約書、合意書、覚書等の書類との違いや法的効力、書き方について。

和解契約書とは和解契約で合意した内容を書面にしたものです。書き方の基本は、「当事者」(誰と誰が),「日付」(いつ),「事実関係」(どんな争いがあって),「和解内容」(話し合いでどのように解決するか)です。和解契約とは、当事者双方が話し合いで互いに譲歩して、その間にある争いを止めることを約束する契約のことをいいます。

仮契約という言葉は広く一般的に使われています。ですが、何故「仮」であるのかを考えて、その効力をはっきりさせる必要があります。たとえタイトルに「仮」と記載されていても、その内容がお互いに何らかの義務を負う内容になっていれば、法的な効力を持つ契約書になります。

利用規約や同意書を作る時に検討する内容や書き方の手順について。WebサービスやWebアプリに限らず、自宅サロンや自宅教室など、ご自身が提供するサービスの利用規約や同意書といった書面を準備していますか?